療育に役立つあそびのアイデア!親子で楽しむ発達支援
 運動療育・運動遊び
運動療育・運動遊びこどもの発達が気になるとき、毎日の生活に手軽に取り入れられる療育のあそびアイデアを知りたいと思いませんか?
この記事では、準備なしですぐに始められる運動あそびや感覚あそびなどを具体的に紹介します。
年齢別のポイントや家庭で続けるコツ、よくある悩みへの回答など、お子さんにあった療育のあそびアイデアがきっと見つかります。
親子などで楽しみながら、こどもの「できた!」を育んでいきましょう!
すぐにできる療育あそびアイデア一覧
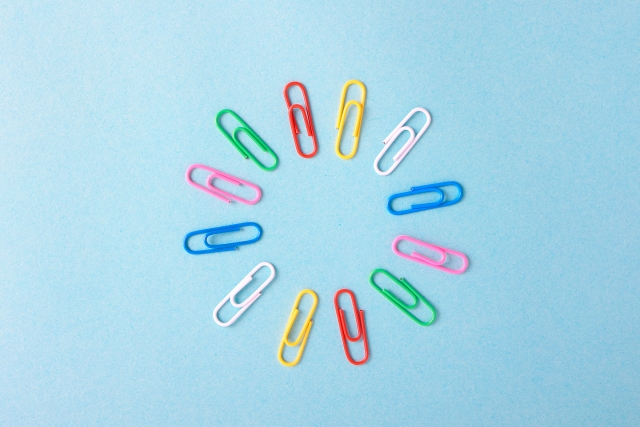
「こどもの発達のために何かしたいけど、何から始めればいいの?」
「特別な道具もないし…」そんなお悩みはありませんか?
専門的な知識や道具がなくても、準備なしや家にある道具などでおうち時間にすぐに取り入れられる療育あそびのアイデアをご紹介します。
あそびを通して楽しく発達支援を行っていきましょう!
感覚あそび(五感を使った体験)
まずは、見る・聞く・触るといった五感を豊かにするあそびから紹介します。
【視覚・聴覚を活用したあそび】
⚪カップタッチあそび(色の識別)
おすすめの年齢: 3歳~小学生
準備するもの: 色つきカップ6個(色紙や折り紙でもOK)
あそび方:
1.カップをいくつか並べます。
2.「赤いカップにタッチして」「青いカップを持ってきて」など、色の指示を出します。
3.こどもは指示された色のカップを見つけてタッチします。
カップの色を見分けて選ぶことで、色の名前を覚えるきっかけになり、見て判断する力も少しずつ育っていきます。こうした体験を積み重ねることで、視覚認知の発達や色の識別力が高まり、さらに集中して取り組む力も伸ばしていくことができます。
⚪音・リズムあそび
おすすめの年齢: 2歳~小学生
準備するもの: 手拍子、タンバリン(あれば)
あそび方:
1.大人が手拍子などで簡単なリズムを叩きます。
2.こどもにそのリズムを真似してもらいます。
3.「早い・遅い」「大きい・小さい」など音に変化をつけると、より楽しめます。
リズムに合わせて音を聞いたり真似をすることで、楽しみながら「聞く力」を養うことができます。繰り返すうちにリズム感が身につき、さらに集中して取り組む姿勢も少しずつ育っていきます。
【触覚・体感覚を育むあそび】
⚪マット感覚あそび
対象: 2歳~小学生
準備するもの: マット、タオル、クッション
あそび方:
マットの上でゴロゴロ転がったり、タオルをかけて隠れたり、クッションに体を預けたりします。
マットやタオル、クッションなどに触れてさまざまな感触を体験することで、触覚が心地よく刺激され、体の位置や動きを感じ取る力(ボディイメージ)が育っていきます。さらに安心して体をゆだねることで、リラックス効果も期待できます。
⚪手あそび・指あそび
対象: 1歳~幼児
準備するもの: なし
あそび方:
「いとまき」や「グーチョキパー」など、昔ながらの手あそび歌を一緒に楽しみます。
昔ながらの手あそびや指あそびは、特別な道具がなくてもすぐに始められます。指先をたくさん使うことで手先の器用さや触覚の発達を促し、大人と一緒に歌ったり言葉をやりとりする中で、自然に言葉の力も育っていきます。
運動あそび(体の使い方を学ぶ)
次に、室内でできる運動あそびで、楽しく体を動かしましょう。
【準備物なしですぐできる運動あそび】
⚪クマさん歩き
おすすめの年齢: 3歳~小学生
場所の目安: 2畳程度のスペース
あそび方:
1.四つん這いになります。
2.両手はパーで床につき、顔は前を向いて進みます。
3.「森の中をのっしのっし歩くクマさんに変身!」など、声かけをすると楽しさアップ。
四つん這いになって歩くことで腕で体を支える力が自然に育ち、体幹もバランスよく鍛えられます。続けるうちに姿勢が安定し、日常生活での転倒予防や正しい姿勢づくりにもつながっていきます。
⚪カンガルー跳び
おすすめの年齢: 4歳~小学生
場所の目安: 3畳程度のスペース
あそび方:
1.両手を胸の前で組みます。
2.両膝をぴったりくっつけて、その場でジャンプします。
3.「お腹に袋がある動物はなにかな?」などクイズ形式で導入するのもおすすめです。
両足をそろえて跳ぶ動きを繰り返すことで、ジャンプする力が育ち、下半身の筋力も自然に強化されます。リズムに合わせて跳ぶことで、楽しく遊びながらリズム感も養われていきます。
⚪ワニさん歩き
おすすめの年齢: 5歳~小学生
場所の目安: 3畳程度のスペース
あそび方:
1.うつ伏せになり、胸と顎を床につけます。
2.腕の力を使って、前に進みます。
3.「ワニさんみたいに静かに進んでみよう」などイメージを伝えます。
床に胸とあごをつけて、腕の力を使って前に進む動きを繰り返すことで、懸垂に必要な腕や上半身の力が育ちます。鉄棒や運動あそびの基礎づくりにもつながり、楽しみながら体の使い方を学んでいくことができます。
【簡単な準備物を使った運動あそび】
⚪方向ジャンプゲーム
対象対象: 4歳~小学生
準備するもの: なし(声かけのみ)
あそび方:
大人が言う「前!」「後ろ!」「右!」「左!」の指示に合わせて、両膝をくっつけてジャンプします。
大人の声に合わせてジャンプすることで、耳で聞いた指示をすぐに判断して動く力が育ちます。繰り返す中で集中力や跳躍力も自然に伸び、遊びながら判断力と体の使い方を身につけていくことができます。
⚪平均台忍者歩き
おすすめの年齢: 4歳~小学生
準備するもの: 平均台(床にビニールテープなどを貼るだけでもOK)
あそび方:
忍者になりきって、平均台(テープ)の上を落ちないようにそーっと歩きます。
【体を大きく使うあそび】
⚪新幹線ウシガエル
おすすめの年齢: 4歳~小学生
準備するもの: 2本のテープ(線路に見立てる)
あそび方:
しゃがんでカエルのポーズになり、テープの線路からはみ出さないようにジャンプして進みます。
カエルのポーズでしゃがみ、線路に見立てたテープの上をジャンプしながら進むことで、体幹がしっかり鍛えられます。線からはみ出さないように意識して跳ぶことで集中力も高まり、跳び箱など次の運動に必要な基礎づくりにもつながります。
おうち時間にすぐに取り入れられる療育あそびのアイデアをご紹介しました。
次に、年齢や発達段階に合わせた工夫ポイントについてご説明していきます。
年齢・発達段階に合わせた療育あそびの工夫ポイント

こどもの成長段階によって、楽しめるあそびや効果的な関わり方は変わっていきます。
せっかく療育あそびををするなら、こどもの成長に合ったものを選びたいですよね。
ここでは、年齢や発達段階、そして「伸ばしたい力」に合わせた療育あそびの工夫についてついて詳しく説明します。
「うちの子にはどのあそびがいいかな?」そんな疑問にお答えします!
幼児期におすすめのあそび(3~6歳)
この年齢は大人の真似っこが得意な時期。
複雑なルールの理解は困難です。
動物の真似など直感的でシンプルな動きが継続しやすく、効果も高い傾向があります。
おすすめの運動あそび
- クマさん歩き: 腕で体を支える力をつけ、転倒予防の基礎を作ります。
- カンガルー跳び: ジャンプ力の基礎を養い、楽しく下半身を強化します。
- 風船あそび: 動くものを目で追いかける力(追視能力)や、目と手を一緒に使う練習になります。
幼児期の療育あそびのポイント
・集中できるのは5~10分
短時間で「「できた!」という達成感を得られるように工夫しましょう。
・「できなくても大丈夫」という安心感を
失敗を怖がる子も多い時期です。
まずは安心できる環境作りが何より大切です。
小学生におすすめのあそび(6~12歳)
発達特性に応じた運動選択
ルールを理解できるようになり、競争をすることも楽しめます。
ただし、個人差が大きいため、勝ち負けよりも「参加すること」を重視する姿勢が、こどものやる気を引き出します。
おすすめの運動あそび
- 方向ジャンプゲーム:指示を聞く力や判断力を養い、集団行動の練習にもなります。
- 平均台あそび各種:バランス感覚と集中力を高め、段階的にチャレンジできます。
- チーム制の風船バレー: 協調性や、自分の役割を理解する力を育みます。
小学生の療育あそびのポイント
・周りと比べない配慮を
他の子と比較し始める年齢だからこそ、苦手なことへの配慮が重要です。
・その子の成長を褒める
「前より上手になったね!」など、ひとりひとりの成長に焦点を当てて褒めることで、継続する意欲に繋がります。
発達領域別の工夫
「ことばの力を伸ばしたい」「集中力をつけたい」など、目的に合わせたあそびを選んでみましょう。
言語を伸ばしたい場合
カップタッチあそび(「あかいカップ」など、物の名前を言いながら遊ぶ)がおすすめです。
すぐに効果は出なくても、3ヶ月ほど続けると語彙の増加が期待できます。
・大人が楽しそうに言葉を使い、自然に真似したくなるような雰囲気を作ります。
集中力を育てたい場合
平均台歩き、方向ジャンプゲームがおすすめです、
まずは「30秒できたらすごい!」など小さな目標からスタート。慣れてきたら少しずつ時間を延ばし、2~3分を目指してみましょう。
・「また挑戦しようね」という前向きな声かけが、次への意欲を育てます。
協調性を高めたい場合
集団での風船バレー、トンネルくぐり、ペアでの運動あそびがおすすめです。
いきなり集団はハードルが高いこともあります。まずは大人と1対1から始め、慣れてから少しずつお友達との関わりを増やしていくのがおすすめです。
昨日できなかったことが今日できた、そんな小さな変化を見逃さずに褒めることが大切です。
年齢や発達段階、そして「伸ばしたい力」に合わせた療育あそびの工夫についてついて詳しく説明しました。
次に、家庭で療育あそびを続けるためのコツと安全対策について紹介していきます。
家庭で療育あそびを続けるためのコツと安全対策

療育あそび・発達支援は、専門機関での療育だけでなく、毎日の暮らしの中で自然に、そして継続的に取り組むことが大切です。
しかし、「どうやって続けたらいいの?」「無理強いになっていないかな?」と不安に感じる保護者の方も少なくありません。
ご家庭で無理なく、そして安全にあそびを通じた支援を続けるための具体的なコツをご紹介します!
こどもの興味に合わせる
こどもの「好き」をあそびの入り口にしましょう!
こどもの「好き」という気持ちをあそびの原動力にします。
大人がやらせたいあそびではなく、こどもが夢中になっているものからヒントを見つけましょう。
例えば、電車が大好きでこだわりを持っているお子さんがいるとします。
その「こだわり」は、こどもの世界を広げる貴重な入り口になります。
【実践例】「電車好き」を活かしたあそびの広げ方
| 領域 | あそびの工夫 |
|---|---|
| 運動・感覚 | プラレールを丁寧につなげることで手先の器用さが育ち、走る電車を目で追うことで見る力も養われます。 |
| 認知・行動 | 色ごとに電車を並べて「これは赤だね」と伝えると色の理解につながり、駅に順番に停める遊びで順序の理解が深まります。 |
| 言葉・コミュニケーション | 「しゅっぱつしんこう!」と一緒に言ったり、「次の駅はどこですか?」とやりとりすることで、言葉の真似や会話の広がりを楽しめます。 |
| 人間関係・社会性 | パパやママと交互に電車を走らせたり、一緒に大きな線路を作ることで、順番を待つ力や協力する力が育ちます。 |
| 生活習慣 | 遊びの終わりに「お片付けの駅に戻そうね」と声をかければ、自然に片付けの習慣を身につけられます。 |
このように、こどもの強い興味は、発達を促す鍵になります。
無理に興味のないことをさせるより、こどもの「好き」の世界を一緒に楽しみながら、少しずつ新しい要素を加えていくことで、こどもは自然に学び、成長していきます。
短時間でも繰り返すことが大切
発達特性のあるお子さんは、一度にたくさんの情報を処理するのが苦手な場合があります。
そのため、「短時間で、繰り返し行う」という方法がとても効果的です。
これは、こどもの集中力が続きすいだけでなく、安心感と達成感にも繋がります。
こどもが見通しを持って取り組めるように環境を整える「構造化」が大切です。
「5分だけパズルをしよう」とタイマーをセットしたり、「この歌が始まったらあそびの時間」と決めたりするのも、構造化の工夫の一つです。
この方法は、具体的な指示でこどもの良い行動を導き、できたらすぐに褒める「ペアレント・トレーニング」の考え方にも通じます。
「部屋を全部片付けて」ではなく、「まず、この箱にミニカーを入れよう」と小さなステップで始め、できたら「できたね!すごい!」とすぐに褒める。
この小さな成功体験の積み重ねが、こどもの自己肯定感を育てます。
毎回同じ手順で、短い時間で行われるあそびは、こどもにとって予測しやすく、安心して参加できます。
一見、進歩がないように感じられても、この安定した土台があってこそ、こどもは新しいことに挑戦するエネルギーを蓄えることができるのです。
安全に配慮する工夫(環境・道具)
こどもがあそびに夢中になるためには、安全な環境が不可欠です。
安全には、
- 物理的な安全
- 感覚的な安全
- 心理的な安全
の3つの側面があります。
1.物理的な安全
怪我を防ぐための基本的な対策です。
・床に危険なものが落ちていないか確認する。
・家具の角にクッション材をつける。
・おもちゃの小さな部品を誤飲しないように注意する。
2.感覚的な安全
こどもにとっては、特定の感覚がとても敏感(過敏)な場合があります。
・視覚過敏:遊ぶおもちゃ以外は片付け、視界に入る情報を減らすと集中しやすくなります。
・聴覚過敏:テレビを消すなど静かな環境を確保したり、イヤーマフを使ったりするのも有効です。
・触覚過敏:粘土などのベタベタした感触が苦手な子もいます。
無理強いせず、保護者が楽しそうに触る様子を見せることから始めましょう。
こどもが不快に感じる刺激を減らし、心地よいと感じる刺激(例:ブランケットにくるまる等)を提供することが大切です。
3.心理的な安全
「失敗しても大丈夫」「ありのままの自分を受け入れてもらえる」と感じられる環境です。
・気持ちに応える:「楽しいね」「これがやりたかったんだね」とこどもの気持ちを言葉にしてあげましょう。
・肯定的な言葉を使う:「ダメ」ではなく、「こうしてみようか」と前向きな言葉で声かけをしましょう。
・無理強いはしない:「やりたくない」という気持ちを尊重し、「じゃあ、今日は見るだけにしておこうか」と受け入れる姿勢が、こどもの安心感を育てます。
これら3つの安全性はお互いに関連しています。
例えば、周りがうるさくて(感覚的に安全でない)落ち着かず、走り回って家具にぶつかり(物理的に安全でない)、結果的に叱られてしまう(心理的に安全でない)という悪循環も考えられます。
「どの安全が足りないのかな?」という視点で観察することで、適切なサポートが見つかります。
最後に、よく寄せられるお悩みについて、Q&A形式でお答えします。
よくある悩みとQ&A
A:「集中力がない」と捉えるのではなく、こどもからのサインとして原因を探ってみましょう。
原因①:あそびが合っていないかも?
⇒こどもが何に夢中になるか観察し、難しすぎる・簡単すぎる場合は難易度を調整しましょう。
複雑なパズルなら、最後の1ピースだけはめてもらうなど、「できた!」と感じられる小さなステップから始めるのが有効です。
原因②周りの刺激が多すぎるかも?
⇒テレビを消し、あそぶおもちゃ以外は片付けて、静かで落ち着いた環境を整えましょう。
原因③:終わりが見えず不安かも?
⇒「この砂時計が落ちるまでね」とタイマーなどを使って、視覚的に時間の見通しを立ててあげると、安心してあそびやすくなります。
何より大切なのは、結果ではなく、プロセスを褒めること。
「5分遊べた」という結果より、「おもちゃに手を伸ばした」という行動そのものを「触ってみたね!えらい!」と具体的に褒めてあげましょう。
A:家庭での準備と、園や学校との情報共有をしていきましょう。
家庭でできる準備
1.スモールステップで慣れる:まずは保護者と1対1で、順番を守るなどの簡単なルールがあるあそびを楽しみます。
慣れてきたら、お友達を1人か2人交えて遊ぶ機会を作りましょう。
2.絵カードなどで「予告」する:これから何が起こるか、どんなルールがあるかを、絵や写真で見せておくと、見通しが立って安心して参加しやすくなります。
園・学校との連携方法
家庭での様子や効果的な支援方法(「タイマーを使うと切り替えがスムーズです」など)を連絡帳や面談で具体的に伝えましょう。
また、こどもの困難を減らすための「合理的配慮」について相談することも大切です。
- ・クールダウンできる空間の確保
- ・なるべく少人数のグループへの所属
- ・「給食係」など具体的な役割の明確化
保護者だけで抱え込まず、まずは関係機関と相談をしてみましょう。
園や学校と協力関係を築いていくことが重要です。
A:発達に特性のあるお子さんの兄弟姉妹(きょうだい児)の気持ちにも配慮し、意図的に関わり方を工夫することが大切です。
親の関わり方の工夫
・「きょうだい児」だけの特別な時間を作る:「今日はあなたと二人だけで公園に行こう」など、短時間でも保護者を独り占めできる時間を作り、大切に思っていることを伝えましょう。
・きょうだい児を「小さな支援者」にしない」:過度に世話やサポートを担わせず、あくまで「きょうだい」として接しましょう。
・それぞれの「良いところ」を言葉にして伝える:「いつも優しくしてくれてありがとう」と感謝を伝えたり、「弟くん、すごいね!」とポジティブな点を伝えたりして、お互いの良い関係を育む手助けをしましょう。
一緒に遊ぶためのヒント
・追いかけっこや風船バレーなど、ルールが単純なあそびを選ぶ。
・一人がブロックを積み上げ、もう一人が壊すなど、役割分担が明確なあそびを取り入れる。
・保護者が「審判」や「実況者」になって、あそびがスムーズに進むようサポートする。
自治体やNPOが運営する「きょうだい会」など、同じ立場のきょうだい児が集まる場に参加し、外部のサポートを活用するのも有効です。
A:診断がなくても、気になることがあれば相談できる場所がたくさんあります。
不安を抱え込まず、まずは身近な公的機関にアクセスしてみましょう。
主な公的相談機関
・市町村保健センター
主な役割:乳幼児健診、育児全般の相談
こんな時に:健診で指摘された時、子育て全般の不安を感じた時
・こども家庭支援センター
主な役割:18歳未満のこどもと家庭に関するあらゆる相談
こんな時に:身近な場所で気軽に相談したい時
・発達障害者支援センター
主な役割:発達障がいに関する専門的な相談・情報提供
こんな時に:専門的な助言や支援機関の情報を得たい時
・児童発達支援センター
主な役割:未就学児への専門的な発達支援
こんな時に:具体的に療育を受けさせたいと考えた時
・教育支援センターなど
主な役割:就学に関する相談、学校生活での困難に関する助言
こんな時に:就学先の選択に悩んでいる時、学校での様子について相談したい時
「気になる」と感じた時が、相談を始める最適なタイミングです。
公的な相談機関は、保護者の不安により沿い、こどもの成長を共に支えてくれるパートナーです。
A:こどもの「こだわり」は、安心感の源であり、大切な土台です。
その世界を無理に変えようとするのではなく、まずは保護者がその世界にお邪魔させてもらう、という気持ちで関わることが出発点になります。
・ステップ1:まずは徹底的に付き合う
こどものこだわりに寄り添い、まずは同じあそびを一緒に楽しみましょう。
「いつも同じだね」と評価するのではなく、「本当にこれが好きなんだね!」「この並べ方、かっこいいね!」と肯定的に受け入れる姿勢が大切です。
保護者が自分の「好き」を共有してくれる存在だと感じることで、こどもは安心し、次のステップに進む心の準備ができます。
・ステップ2:少しだけ新しい要素をプラスする
こどものあそびの世界観を尊重しながら、ほんの少しだけ新しい要素を加えてみましょう。
・物の追加:いつもミニカーを一列に並べているなら、その隣に小さなトンネルや信号のおもちゃをそっと置いてみる。
・言葉の追加:「ブッブー、速いね。次はトンネルをくぐりまーす」と実況中継してみる。
・動きの追加:保護者が別のおもちゃで、こどもの真似をしてみる。
ここでポイントは、こどもがその新しい要素に興味を示さなくても気にしないことです。
あくまで「こんなのもあるよ」と提案するだけ。
もしこどもが嫌がったら、すぐに元に戻しましょう。
このさじ加減が、こどもの世界観を尊重しつつ、興味を広げる鍵となります。
・ステップ3:偶然を装って変化を起こす
あそびの中に、偶然を装って少しの変化を取り入れてみるのも良い方法です。
例えば、ブロックを積んでいる最中に、保護者が「おっと!」と違う形のブロックを落としてみる。
「あ、こんなブロックも混ざってたね。これはどこに置こうか?」と問いかけることで、いつもと違うパターンを試すきっかけが生まれるかもしれません。
こどもの「こだわり」は、決してネガティブなものではありません。
それは、こどもなりの楽しみ方であり、学び方です。
そのこだわりを「出発点」として、保護者が少しずつ新しい世界への橋渡しをしてあへることで、こどものあそびは豊かに広がっていきます。
ここまで、たくさんの情報がありましたが、最も大切なことは、保護者の方が一人で抱え込まず、まずがご自身が安心できることです。
保護者の心の安定が、こどもの健やかな成長に不可欠だからです。
- ・こどもの「好き」に寄り添い、
- ・短時間でもいいから繰り返し、
- ・物理的・感覚的・心理的に安全な環境を整える。
これらの工夫はすべて、こどもとの間に安心できる信頼関係を築くためのものです。
思うようにいかない日があっても、自分を責める必要はありません。
今日1分、こどもと笑い合えたなら、それは素晴らしい発達支援です。
日々の暮らしの中にあるこどもの「できた!」をひとつひとつ、大切に育んでいきましょう!
「こどもプラス」では、運動あそびを通じて、こどもひとりひとりの発達段階に合わせた支援を提供しています。
こどもが「楽しい!」と感じる活動の中で、無理なく集中力や社会性を育んでいくことを大切にしています。
専門の知識を持ったスタッフが、お子さんの「できた!」という成功体験を一つひとつ丁寧に積み重ね、自信を持って成長していけるようサポートします。
ご興味のある方は、ぜひお近くの「こどもプラス」の教室まで、お気軽にお問い合わせください。
見学や体験も随時受け付けております!





