ADHDの癇癪…どう対応すればいい?原因を知って上手につき合う方法
 ADHD
ADHD「うちの子、どうしてこんなにすぐカッとなるんだろう…」
「一度泣き出すと手がつけられない…」
こどもの激しい癇癪に、どう対応していいか分からず、途方に暮れてしまうことはありませんか?
その「癇癪」は、単なるわがままや性格の問題ではなく、ADHD(注意欠陥・多動性障害)の特性が影響しているのかもしれません。
ADHDのこどもが癇癪を起こしやすいことは、多くの保護者の方が抱える共通の悩みです。
大切なのは、その敗勢にある原因を正しく理解し、適切な対応方法を知ることです。
そうすることで、こども自身も、そして家族の日常も、ずっと楽になるはずです。
一人で抱え込まず、一緒に学んでいきましょう。
ADHDと癇癪の関係をわかりやすく解説
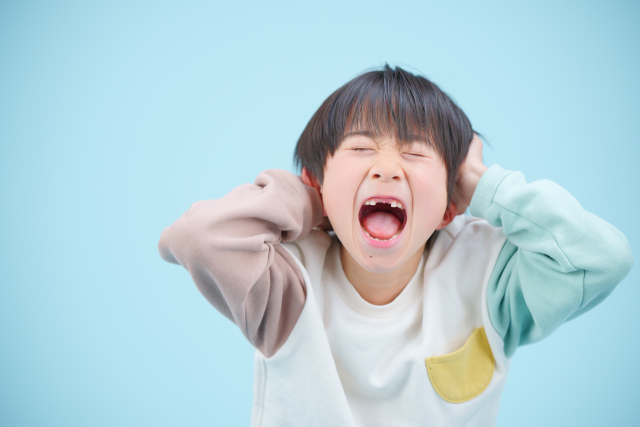
なぜADHDのこどもは、癇癪を起こしやすいのでしょうか。
まずは、ADHDの特性と脳の働きから、その関係性を紐解いていきましょう。
ADHDの特性(注意欠如・多動性・衝動性)
ADHDは、生まれつきの脳機能の発達のかたよりによる発達障がいの一つです。
その特性は大きく以下の3つに分けられます。
- 不注意・・・集中力が続かない、忘れ物が多い、話を聞いていないように見える。
- 多動性・・・じっとしていられない、そわそわと手足を動かす、おしゃべりが止まらない。
- 衝動性・・・順番を待てない、思ったことをすぐ口に出す、相手の話を遮って話し始める。
これらの特性の現れ方には個人差があり、全ての特性が同じように強くでるわけではありません。
中には、診断名はつかなくても、これらの傾向(いわゆるグレーゾーン)によって、日常生活の困り事を抱えているこどももいます。
ADHDと癇癪が起きやすい理由
ADHDのこどもが癇癪を起こしやすいのは、特に「衝動性」の特性が大きく関係しています。
「嫌だ!」「やりたい!」といった感情が湧き上がったとき、その気持ちを抑えたり、言葉で適切に伝えたりすることが苦手なため、行動や感情が爆発という形で現れてしまうのです。
また、「不注意」によって指示が聞き取れずに行動して叱られたり、「多動性」によって静かにすべき場面で動いてしまったりと、特性が原因で周囲から否定的な言葉をかけられる経験が多くなりがちです。
そうした積み重ねが、ストレスや自己肯定感の低下につながり、ささいなことで感情が爆発しやすくなる一因ともなります。
脳の働きと感情コントロールの仕組み
私たちの脳には、感情や行動をコントロールする「司令塔」の役割を果たす前頭前野という部分があります。
ADHDのこどもの場合、この前頭前野の働きに何かのかたよりがあると考えられています。
そのため、カッとなったときに「一旦落ち着こう」と考えたり、自分の気持ちを客観的に見つめたりすることが、脳の機能的に難しいのです。
ADHDの癇癪は、脳の機能的な特性によるものであり、本人の気持ちの持ちようや、しつけの問題ではありません。
そのことを理解してあげることが、適切なサポートの第一歩となります。
ADHDの癇癪の原因と前兆サイン

ADHDのこどもの癇癪は、さまざまな要因が引き金となって起こります。
その原因を知り、癇癪が起きる前のサインに気づくことができれば、大きな爆発を防ぐことにつながります。
環境要因・心理要因・社会要因
癇癪の引き金は、一つだけではありません。
以下のような要因が複数に絡み合っています。
| 要因の種類 | 具体例 |
| 環境要因 | ・騒がしい場所、人混みなど、感覚的な刺激が多すぎる ・急な予定変更で、見通しが立たなくなった ・気温の変化(暑い・寒い) |
| 心理要因 | ・自分の気持ちをうまく言葉で表現できない ・思い通りにいかない ・失敗体験の積み重ねによる自己肯定感の低下 ・疲れや眠気 |
| 社会要因 | ・友達とのトラブル ・ルールが理解できず、集団行動についていけない ・周囲からの誤解や否定的な評価 |
癇癪が起きる前のサインを見極める
感情が爆発する前には、こどもなりのサインが出ていることが多くあります。
日頃からよく観察し、早めに気づいてあげることが大切です。
- 行動のサイン・・・貧乏ゆするが激しくなる、指をいじる、部屋をうろうろし始める
- 言葉のサイン・・・口数が少なくなる、または逆に攻撃的な言葉が増える、「どうせ」「だって」といった否定的な言葉を繰り返す
- 表情・態度のサイン・・・眉間にしわが寄る、口がへの字になる、返事をしない、目を合わせなくなる
これらのサインが見られたら、「何か嫌なことがあったのかな?」と、本格的な癇癪になる前に介入するチャンスです。
家庭・学校でよくある具体例
【家庭での例】
宿題を始めようとしたが、どこから手をつけていいか分からず混乱。
親に「早くやりなさい!」と急かされ、「もうやらない!」とノートを投げつけて癇癪を起こす。
【学校での例】
休み時間に友達と遊んでいて、ルールが分からず友達に「違うよ!」と強く居笑えたことにカッとなり、相手を押してしまう。
ADHDの癇癪への正しい対応方法

実際に癇癪が起きてしまったとき、どのように対応すればよいのでしょうか。
癇癪が起きたとき、パニックにならず、冷静に対処するためのポイントをご紹介します。
癇癪が起きたときに親・支援者ができること
一番大切なのは、安全の確保です。
こども自身や周りの人が怪我をしないことを最優先に考えましょう。
①安全な場所へ移動する
物を投げたり、暴れたりする可能性がある場合は、周りに危ないものがない、静かで落ち着ける場所(クールダウンできるスペース)へ本人を誘導します。無理に動かせない場合は、周りの危険なものを片付けましょう。
②冷静に見守る
激しく興奮している最中に、言い聞かせようとしたり、理由を問詰めたりするのは逆効果です。感情の嵐が過ぎ去るのを、黙って静かに見守りましょう。「そばにいるよ」という姿勢を示すだけで十分です。
③落ち着いてから話をする
興奮が収まり、話が聞ける状態になってから、「さっきはびっくりしたね」「何が嫌だったか教えてくれる?」と、穏やかに気持ちを尋ねます。このとき、行動を責めるのではなく、その背景にある感情に寄り添うことが重要です。
言葉かけと環境調整のコツ
癇癪を呼ぼうし、こどもが安心して過ごせるようにするためには、日々の「言葉かけ」と「環境調整」がとても重要です。
| 工夫のポイント | 具体的な内容と理由 |
| 1.肯定的な言葉かけ | 「~ダメ」という否定的な言葉ではなく、「~しようね」としてほしい行動を具体的に伝えます。
(例:「走っちゃダメ」→「廊下は歩こうね」) |
| 2.短い言葉で伝える | 長い説明や一度の多くの指示は、特性上、伝わりにくいことがあります。 指示は短く区切って、シンプルに伝えましょう。(例:「おもちゃ、箱に、どうぞ」) |
| 3.刺激を減らす | テレビの音、散らかったおもちゃなど、周囲の刺激は集中を妨げ、イライラや興奮の原因になりやすいです。落ち着きやすい環境を整えましょう。
(例:集中させたい時はテレビを消す、遊ぶおもちゃ以外は片付ける) |
| 4.見通しを持たせる | 「次に何が起こるか分からない」という不安は、癇癪の引き金になります。 絵や写真を使ったスケジュール表で予定を視覚的に伝えることで、こどもは安心して行動できます。(例:朝の支度、1日の流れなどを絵カードで示す) |
ADHDの癇癪を予防する日常の工夫

ADHDの癇癪は、生活リズムを整え、感情コントロールの練習や適切な運動を取り入れることで、未然に防ぐことができます。
日常生活の中でできる工夫を取り入れてみましょう。
生活リズムとルールの整え方
癇癪を未然に防ぐためには、日々の生活の土台を整え、こどもの自己肯定感を育てることが大切です。
ここでは、家庭ですぐに取り組める「生活リズム」「ルール」「成功体験」に関する3つの工夫をまとめます。
| 工夫のポイント | 具体的な内容とねらい |
| 1.生活リズムを整える | 決まった時間に寝起きします。 安定した生活リズムは、心と体の土台を作ります。特に睡眠不足は感情の不安定さに直結するため、睡眠時間の確保は非常に重要です。 |
| 2.ルールはシンプルに | 家庭内のルールは、「守れる」ことを前提に、少なく、分かりやすく設定します。 ルールを守れたときは、たくさん褒めてあげることで自己肯定感を育みます。 |
| 3.成功体験を増やす | 少し頑張れば達成できるような小さなお手伝いを頼むなど、こどもが「できた!」と感じられる機会を意識的に作りましょう。 これが自信につながります。 |
感情コントロールを身につける練習
自分の気持ちに気づき、客観的に捉えることは、感情をコントロールするための大切な第一歩です。
日常生活の中で、遊び感覚で取り入れられる簡単な練習方法をご紹介します。
①感情のラベリング
こどもがイライラしたり、悲しんでいるときに、「今、悔しい気持ちなんだね」「悲しかったんだね」と、大人が感情を言葉にしてあげることで、自分の気持ちに気づく練習になります。
②気持ちの温度計
怒りの度合いを温度計のイラストなどで視覚化し、「今のイライラは何度くらい?」と尋ねることで、自分の感情を客観視する手助けになります。
ADHD特性に合わせた運動あそびの紹介
こどもが興奮しているときは、単一の運動だけで対応するより、段階的に複数の運動を組み合わせる方が効果的です。
最初に体内のエネルギーを発散させ、その後に体幹や神経系を整える運動を行うことで、自然に落ち着いた状態へ導くことができます。
ここでは、具体的なステップの例を紹介します。
ステップ①カンガルー跳び(3〜5分)
最初に行うのはカンガルー跳びです。
こどもが体に溜め込んだエネルギーを安全に発散させることができます。
特にADHDの子どもは体内にエネルギーが蓄積されやすく、それが癇癪の原因になることもあるため、まずこの段階で十分に消費させることが重要です。
▼あそび方
- 「お腹に袋のあるカンガルーに変身しよう」と声をかけ、両膝をくっつけて手は胸の前にした姿勢でジャンプします。始める前に「魔法ののり」で膝をくっつける演出をすると、楽しみながら正しい姿勢を維持しやすくなります。
この運動により跳躍力の向上と同時に、興奮したエネルギーを効果的に発散できます。
こどもの表情や呼吸が落ち着き始めたタイミングで次のステップに進むのが目安です。
ステップ②クマさん歩き(2〜3分)
次に行うのがクマさん歩きです。
全身の協調性を向上させ、体幹の安定させることができます。
カンガルー跳びで上下方向のエネルギーを使った後は、水平方向の動きで体全体のバランスを整えます。
▼あそび方
- 四つんばいの姿勢で手はパーにし、顔は前向きにして「のっしのっし歩く大きなクマさん」になりきります。腕の支持力が向上すると同時に、全身への適度な圧迫感覚で神経系の興奮を徐々に鎮める効果があります。
こどもの動きが安定して呼吸が深くなってきたことを確認しながら、次のステップへの準備が整ったかを見極めます。
この段階で多くのこどもは表情が和らぎ、周囲への注意も向けられるようになります。
ステップ③ワニさん歩き(2〜3分)
最後に行うワニさん歩きは、神経系の鎮静と集中力の向上を目的としています。
カンガルー跳びやクマさん歩きに比べて最もゆっくりとした動作が求められるため、自然にペースコントロールを身につけることができます。
▼あそび方
- うつ伏せで胸と顎を床につけ、手の力だけで進む動作を「水の中でそっと獲物を狙うワニさん」とイメージさせると、子どもは自然とゆっくりと動くことを意識します。これにより衝動的な行動を抑える力も育まれます。
こどもが落ち着いて集中しているかを確認することで、この運動の効果を実感できます。
多くの場合、このステップを終える頃には、開始時とは明らかに異なる落ち着いた状態になっています。
ADHD癇癪Q&A・よくある悩みの解決事例

ADHDの特性を理解していても、日常生活の場面で、「どう対応すればいいの?」と悩んでしまうことは多いものです。
ここでは、よく寄せられるお悩みについて、具体的な対策をご紹介します。
夜寝る前に癇癪が起きるときの対策
A.就寝前の癇癪は、1日の疲れや刺激が原因であることが多いです。
入眠儀式(スリープセレモニー)を取り入れ、心と体をリラックスモードに切り替える工夫をしましょう。
▼具体的な工夫
- 寝る1時間前にはテレビやスマート、ゲームをやめる。
- お風呂にゆっくり入る、絵本を読む、静かな音楽を聴くなど、毎日同じ流れで過ごす。
- アロマを焚いたり、軽いマッサージをしたりして、感覚的にリラックスできる環境を作る。
学校で怒りが爆発するときの対策
A.学校は、家庭と違って「思い通りにならないこと」や「感覚的な刺激」が非常に多い場所です。
学校でのトラブルは、こども一人で解決するのが難しい場合がほとんどです。
学校との連携が不可欠になります。
▼具体的な工夫
- 担任の先生やスクールカウンセラーに、こどもの特性や家での様子を伝え、癇癪が起きやすい状況を共有する。
- 興奮したときに一人で落ち着ける場所(例:保健室、相談室など)を、あらかじめ先生と相談して決めておく。
- 学校生活での困りごとを減らすための支援をまとめた「個別の教育支援計画」の作成を相談する。
家庭と学校で対応が違うときの工夫
A.対応に一貫性がないと、こどもは混乱していまいます。
一方で、「外(学校)では頑張って、家(安心できる場所)で爆発する」というケースも非常に多いです。
家庭と学校が同じ方向を向いて支援できるよう、情報共有の仕組みを作りましょう。
▼具体的な工夫
- 連絡帳や支援ノートを活用し、「家ではこう対応したらうまくいきました」「学校ではこんなことがあって疲れているようです」など、具体的な情報をこまめに交換する。
- 定期的に面談の機会を設け、こどもの成長や課題について、双方の認識をすり合わせる。
- 地域の発達障がい者支援センターなどの専門機関に相談し、第三者として間に入ってもらうことも有効な手段です。
ADHDのこどもの癇癪への対応は一人で抱え込まず、家庭・学校・専門機関が連携しながら、こどもの成長を見守ることが大切です。
こどもの癇癪と向き合うことは、決して簡単なことではありません。
しかし、正しい知識を持ち、周囲と協力しながら適切なサポートを続けることで、こどもは少しずつ感情をコントロールする力を身につけていきます。
一人で抱え込まず、利用できる支援は積極的に活用しながら、こどもの成長を温かく見守っていきましょう。
クマさんに関する運動遊びをもっと知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。





