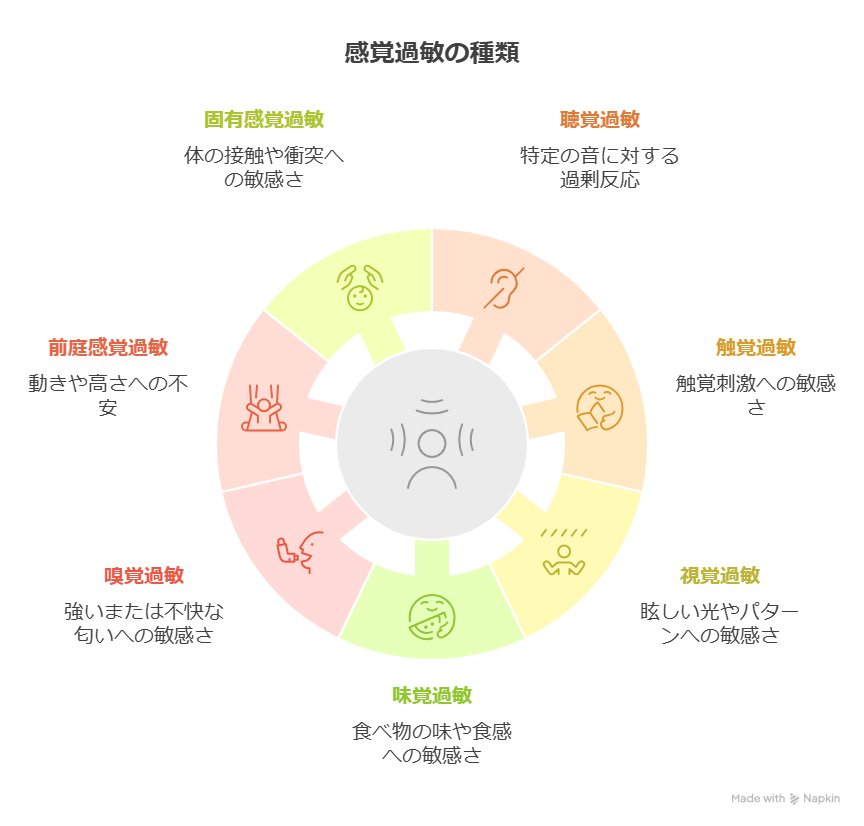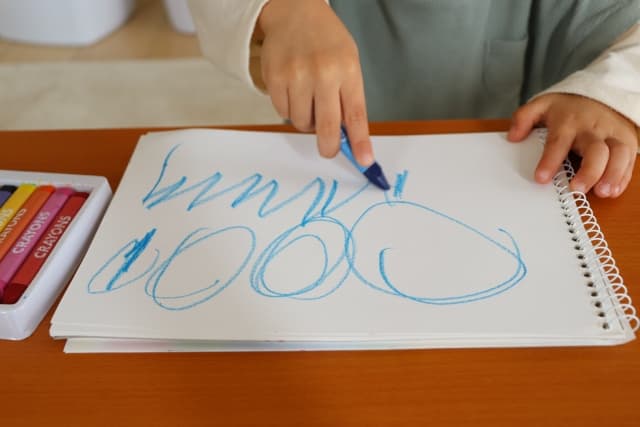感覚過敏=発達障がいではない!こどもの感覚特性を正しく理解する
 発達障害
発達障害「うちの子、音に敏感すぎて心配…」「服のタグが気になって大泣きしちゃうんです」「これって発達障がいのサインでしょうか?」
安心してください、こんな悩みを抱えているご両親は、とても多いんです。
私自身、10年以上発達障がい支援の現場で働いてきて、感覚過敏についての心配の声をたくさん聞いてきました。
でも、感覚過敏があるからといって、必ずしも発達障がいではないんです。
この記事では、感覚過敏について、発達障がいではない場合も含めてわかりやすくお話ししていきます。
結論:感覚過敏は発達障がいを意味するものではない
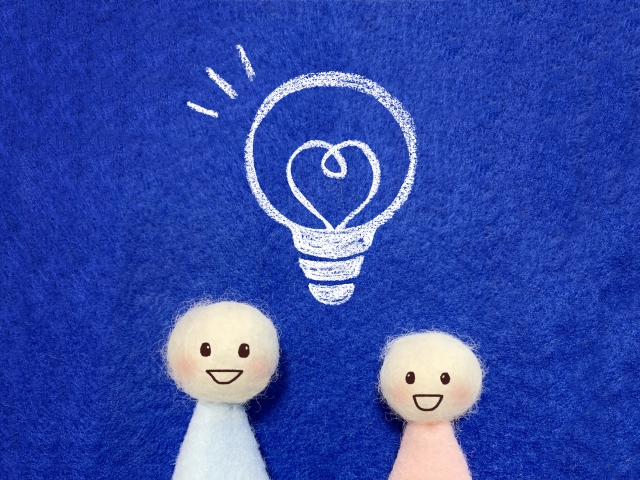
まず最初に、心配されているご家族に伝えたいことがあります。
お子さんに感覚過敏があっても、それだけで発達障がいだと決めつける必要はまったくありません。
感覚過敏は、発達障がいのお子さんにもよく見られますが、実は「定型発達」と言われるこどもたちにもかなり広く見られる特性です。
国立精神・神経医療研究センターの調査(2018)によると、一般的な発達をしているこどもたちの15〜20%程度にも何らかの感覚過敏が見られることがわかっています。
5人に1人くらいはいるということですから、決して珍しくないのです。
感覚過敏と発達障がいの関係に関する最新見解
最新の研究では、感覚過敏は「脳の発達の多様性」として捉えられるようになってきています。
専門家の間でも、「感覚過敏があるだけでは発達障がいとは言えない」という考えが主流になっています。
日本感覚統合学会の報告でも、感覚過敏は単独の特性としてよく見られるもので、必ずしも発達障がいを示すわけではないとされています。
「敏感な子」というのは、昔から普通にいたのです。
感覚過敏があるこどもの多くは発達障がいではないという事実
数字で見るとさらに安心できるかもしれません。
東京都の児童発達支援センターでの調査によれば、感覚過敏のあるこどもたちのうち、約7割は発達障がいの診断基準を満たさないことがわかっています。
つまり、感覚過敏があるこどもの大部分は発達障がいではないのです。
必要以上に心配しすぎず、「こどもの個性のひとつ」という気持ちで、どうやってサポートしてあげられるかを考えていくとよいでしょう。
感覚特性の個人差としての感覚過敏の位置づけ
考えてみてください。大人でも、「この服の素材は気持ち悪い」とか「この音は耐えられない」といった感覚の好き嫌いがありますよね。
電車の中で誰かがガムを噛む音に敏感で、聞こえるとイライラしてしまう人もいます。
こうした感覚の感じ方は本当に人それぞれです。
研究者の中には「感覚プロファイル」という言葉を使って、「誰にでも固有の感覚特性がある」と説明する方もいます。
つまり、お子さんの感覚過敏も、その子ならではの個性の一部だと考えられるのです。
保護者が知っておくと安心できる基本ポイント
感覚過敏について知っておくと安心できるポイントをいくつか挙げます。
- 感覚過敏はこどもの成長とともに変化・改善することが多いです(多くの場合は和らいでいきます)
- 環境をちょっと工夫するだけで、グッと楽になることもあります
- 敏感な感覚は、将来素晴らしい才能になることもあります(芸術家や料理人など)
- 早めに理解して対応してあげると、お子さんも楽になります
ぜひ知っていただきたいのは、感覚過敏があることは発達障がいを意味するものではなく、むしろ「人それぞれ違って当たり前」という多様性の一部だということです。
それでは次に、こどもの感覚過敏とは具体的にどのようなものなのか、もう少し詳しく見ていきましょう。
感覚過敏とは?こどもの感覚特性を理解する
感覚過敏とは、簡単に言うと「特定の感覚刺激に普通の子よりも強く反応してしまう特性」のことです。発達障がいではありません。
発達はごく普通でも、特定の音や触感に「とても敏感」というこどもは少なくありません。
こどもの感覚過敏の定義と具体的な現れ方
感覚過敏は、こんな風に現れることが多いです。
- 聴覚過敏:「掃除機の音が怖い」「花火大会に行けない」など特定の音に過剰反応
- 触覚過敏:「このシャツのタグがチクチクする」「髪を切るのが嫌」など触感に敏感
- 視覚過敏:「この光眩しすぎる」「このパターン見ているとクラクラする」など視覚刺激に敏感
- 味覚過敏:「この食感が苦手」「混ざり物が口に入ると気づいてしまう」など食べ物の味や感触に敏感
- 嗅覚過敏:「このニオイが気持ち悪い」と大人が気にならないような匂いに反応
- 前庭感覚過敏:「ブランコが怖い」「高いところが苦手」など回転や高さに不安を感じる
- 固有感覚過敏:「ハグされるのが嫌」「ぶつかるのが嫌」など身体の位置感覚が敏感
例えば、あるクラスの女の子は、聴覚がとても敏感で、教室の蛍光灯から出るかすかな「ジー」という音(大人はほとんど気づかない音です)が気になって集中できませんでした。
座る位置を工夫したり、少しずつ慣れる練習をしたりして、今ではすっかり問題なく過ごせるようになっています。
年齢別に見られる典型的な感覚過敏の症状
感覚過敏は、こどもの年齢によって現れ方が変わってきます。
赤ちゃんの頃(0〜3歳)
- ドロドロした食感を強く嫌がる
- 特定の抱っこの仕方でないと機嫌が悪くなる
- 突然の音に過剰にビクッとする
幼稚園くらいの頃(3〜6歳)
- 集団活動の音に対して耳をふさぐ
- 特定の服を着るのを頑固に拒否する
- 公園のトイレの自動水洗の音に恐怖を感じる
小学生(6〜12歳)
- 蛍光灯のわずかな点滅に気づく
- 給食の特定の料理だけを避ける
- 身体接触のある活動に不安を感じる
小児医学の研究によると、3歳くらいまでは感覚過敏が一時的に増えることが多いそうです。
しかし、その後は少しずつ慣れていくケースが多いとのこと。
これは、脳が成長して感覚情報をうまく処理できるようになってくるためです。
感覚過敏の脳科学的メカニズム
私たちの脳は、外からの情報を「これは大事」「これは無視していいや」と仕分ける作業をしています。
感覚過敏がある場合は、この「仕分け作業」のやり方が少し違います。
研究によると、感覚過敏のあるお子さんは、脳の中の「情報フィルター」の働き方に個性があるのだそうです。
これは「病気」ではなく、脳の「個性」の一つと考えられています。
例えるなら、一般的なこどもの脳が「音量50のスピーカー」だとしたら、感覚過敏のあるお子さんの脳は「音量70のスピーカー」のような感じかもしれません。
小さな音も大きく聞こえるため、敏感に反応するわけです。
こどもの感覚過敏は治るのか?
「うちの子だけかな?」と心配される方も多いですが、実はかなりの数のお子さんが感覚過敏の特性を持っています。
近年の調査では、
- 赤ちゃん〜幼児期:約25〜30%(4人に1人くらい)
- 幼稚園〜保育園の頃:約20〜25%(5人に1人くらい)
- 小学生の頃:約15〜20%(6〜7人に1人くらい)
- 中学生以降:約10〜15%(10人に1〜1.5人)
と、成長するにつれてその割合は徐々に減っていくことがわかっています。
つまり、感覚過敏は「治る」というよりも、年齢とともに「落ち着いていく」「気にならなくなる」ケースが多いのです。
脳の発達とともに、感覚の情報処理が上手になり、少しずつ生活のしづらさが和らいでいきます。
「そのうち慣れるかも」という親御さんの希望は、実は科学的にも根拠があるんですね。
感覚過敏は発達障がいがあってもなくても見られる特性で、多くのこどもたちは成長とともに上手に付き合えるようになっていきます。
次は、発達障がいと感覚過敏の関係についてもう少し詳しくお話ししましょう。
「発達障がい」と「感覚過敏」何が違うの?
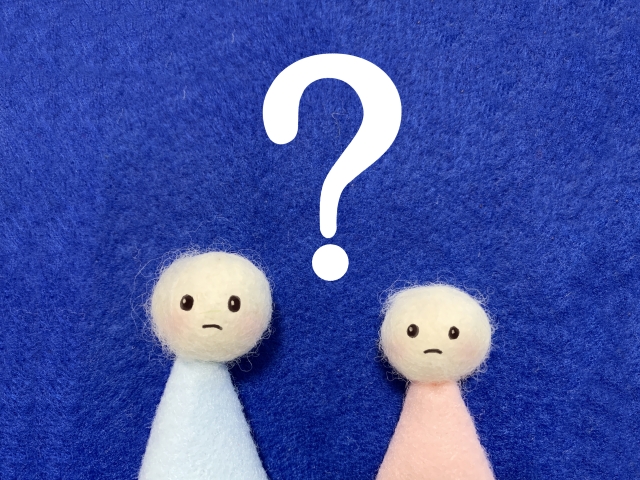
「感覚過敏があるから発達障がいかも…」と心配される方は多いです。
感覚過敏は確かに発達障がいのあるお子さんによく見られますが、感覚過敏があるだけで発達障がいと診断されることはありません。
実際に発達支援の現場で働いている立場から見ても、この二つはしっかり区別して考えるべきものです。
発達障がいにおける感覚過敏の特徴と位置づけ
発達障がい(自閉スペクトラム症やADHD、学習障害など)では、確かに感覚過敏の特性を持つお子さんが多いです。
自閉症学会の報告では、自閉スペクトラム症のお子さんの約70〜90%に何らかの感覚過敏が見られるとされています。
しかし、発達障がいのあるこどもの場合、感覚過敏は「全体像」の一部に過ぎません。
発達障がいのあるお子さんの感覚過敏には、こんな特徴があることが多いです。
- ひとつではなく、複数の感覚領域で過敏さが見られる(音も光も触感も…)
- 社会性やコミュニケーション、行動面の特徴と一緒に現れる
- 長い期間、変わらず続くことが多い
- 環境を変えるだけではなかなか良くならないことがある
つまり、感覚過敏が「単独」で現れるのか、「他の様々な特徴と一緒」に現れるのかが、大きな違いです。
発達障がいの診断基準と感覚過敏の関係
実際のところ、発達障がいの診断はどのように行われるのでしょうか?医師たちはDSM-5という「診断のための手引き」を参考にしています。
その中の自閉スペクトラム症の診断基準には、確かに「感覚刺激への過敏さや鈍感さ、環境の感覚的側面への並外れた興味」という項目が含まれています。
しかし、国立精神・神経医療研究センターの診断ガイドラインでは、はっきりと「感覚過敏だけでは発達障がいと診断しない」と記されています。
診断には、他の中核的な特徴(社会的コミュニケーションの質的な違いや、限定的・反復的な行動パターンなど)が必要です。
要するに、感覚過敏は発達障がいの「可能性を示すヒントのひとつ」ではあっても、それだけで「発達障がいだ」とはならないのです。
感覚過敏だけでは発達障がいと診断されない理由
発達障がいの専門クリニックで10年以上働いている小児科医は、こう説明しています。
- そもそも感覚過敏は一般のこどもにもよくある特性です(幼児期なら4人に1人くらい)
- 発達障がいは感覚だけでなく、社会性や認知、行動など、様々な面で特徴が見られるものです
- 感覚過敏は、ある時期だけ強く出て、成長とともに落ち着くこともよくあります
- 環境や心理的な要因(ストレスや不安など)でも感覚過敏は起こることがあります
外来には「うちの子、耳を塞いで嫌がるから発達障がいでしょうか?」と心配されて来られる保護者も多いそうですが、詳しく見ていくと発達障がいではないケースも多いとのことです。
発達障がい診断における他の必要条件
実際に発達障がいの診断を受けるには、感覚過敏以外にも以下のような特徴が見られるかどうかが重要です。
- 自閉スペクトラム症の場合:「人との関わり方が独特」「コミュニケーションの取り方に特徴がある」「興味や活動が限られる・同じことを繰り返す」といった特徴
- ADHDの場合:「注意が続かない」「じっとしていられない」「考える前に行動してしまう」といった特徴が続く
- 学習障害の場合:「特定の学習(読み書き計算など)を習得するのが難しい」
そして、これらの特徴が「日常生活や学校生活で困ることにつながっている」必要があります。
感覚過敏があっても、こうした中核的な特徴がなければ、発達障がいとは診断されません。
感覚過敏は発達障がいの一つの特徴ではありますが、感覚過敏があるだけでは発達障がいと診断されることはありません。
次は、感覚過敏が発達障がい以外に、どんな原因で起こりうるのか見ていきましょう。
こどもの感覚過敏が発達障がいではない場合
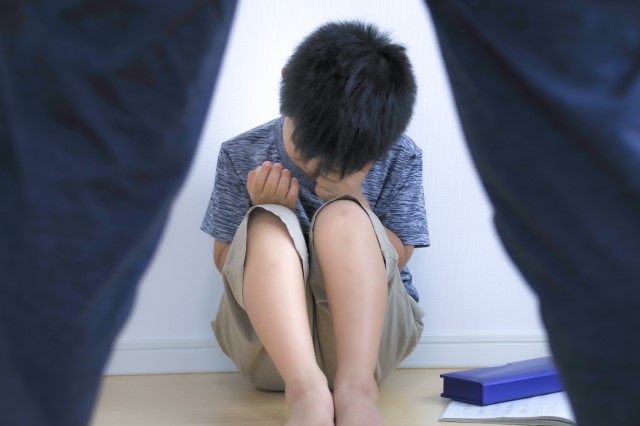
こどもの感覚過敏が発達障がいではない場合が多く、実はそれ以外にもたくさんの原因があります。
多くの場合、一時的な発達の段階や環境の影響によるものです。
特定の時期だけ感覚過敏が目立ったり、環境を少し変えただけでグッと楽になったりするケースも少なくありません。
発達段階に応じた感覚処理能力の未熟さ
こどもの脳は、成長する過程で「感覚情報の処理の仕方」を学んでいきます。
それはちょうど、ピアノの練習と同じで、最初はぎこちなくても少しずつ上手になっていくのです。
国立成育医療研究センターの研究によると、特に2〜4歳頃は「感覚統合能力」(いろんな感覚をまとめて処理する力)がまだ発達途上。
だから、この時期は一時的に感覚過敏が増えることが多いのです。
例えば:
- 赤ちゃんが急な音にビクッとするのは、聴覚系がまだ発達中だから
- 幼児が「このネバネバ食べられない!」と言うのは、口の感覚がまだ発達中だから
- 小さい子が「触らないで!」と言うのは、触覚系がまだ発達中だから
これらは「問題」や「病気」ではなく、成長過程で当たり前に起こることです。
3歳の頃はハンドドライヤーの音が怖くて泣いていた子も、小学生になると全く気にならなくなることもよくあります。
遺伝的要因・気質(性格)による感覚特性の個人差
感覚の敏感さは、実はかなり遺伝の影響を受けています。
「この子は誰に似たんだろう?」と思うことはありませんか?研究でも、親子の間で感覚特性がよく似ていることがわかっています。
また、生まれつきの気質(性格のようなもの)と感覚過敏には深い関係があります。
- 「慎重さん」タイプのお子さんは、新しい刺激に敏感に反応しやすい
- 「様子見派」のこどもは感覚過敏を示すことが多い
- 「感情表現が豊か」なお子さんは、感覚入力に対しても強く反応する傾向がある
あなたのお子さんの感覚過敏は、その子の生まれ持った「気質」の表れかもしれません。
音に敏感な親から生まれたこどもも、同じように音に敏感なことが多いのです。
こうした特性は、「困ったこと」というより「その子らしさ」と考えられます。
環境要因(過剰刺激・不規則な生活リズムなど)
現代のこどもたちを取り巻く環境も、感覚過敏に大きく影響しています。
- デジタル機器の普及:スマホやタブレットからの強い光や音の刺激
- 都会の刺激:街の騒音、人混み、まぶしい看板や照明など
- 生活リズムの乱れ:寝不足だと感覚が敏感になりやすい(大人も経験があるでしょう)
国立環境研究所の調査では、都会に住むこどもは田舎のこどもよりも一時的な感覚過敏を示す割合が1.5倍も高かったそうです。
これは、環境の影響が大きいことを示しています。
実際、GWや夏休みの後に「なんだか敏感になっている」というこどもも少なくありません。
生活リズムが乱れると、こどもは感覚に敏感になりやすいのです。
しかし、規則正しい生活に戻るとすぐに落ち着くことも多いです。
心理的要因(不安・ストレス・過去の体験など)
こどもの心の状態も感覚過敏に大きく影響します。
これは大人も同じですね。ストレスがたまっているときは、ちょっとした音にもイライラしたりしませんか?
- ストレスがあると:体内でストレスホルモンが出て、感覚が敏感になります
- 不安を感じていると:脳が「危険を察知するモード」になって、ちょっとした刺激にも過剰反応します
- 怖い体験をした後は:その体験に関連する感覚に特に敏感になることもあります
小児精神医学の研究では、引っ越しや転校などの大きな環境変化を経験したこどもが、しばらくの間感覚過敏を示すことがよくあるとわかっています。
例えば、病院での嫌な体験の後、医療機関特有の消毒液の匂いにとても敏感になったこどもも、少しずつ慣らしていくことで、数ヶ月でだいぶ落ち着くことがあります。
感覚過敏は発達障がいだけでなく、成長段階、遺伝的要因、環境要因、心の状態など、いろんな理由で生じる可能性があります。
次に、お子さんの感覚過敏をどうやって見極めればいいのか、具体的なポイントをお話しします。
こどもの感覚過敏の見極め方

「うちの子、わがままなのかな?それとも感覚過敏なのかな?」と悩むことも多いでしょう。
感覚過敏はただの「わがまま」ではなく、お子さんが本当に不快に感じている状態です。そして、発達障がいとは必ずしも結びつきません。
見極めるには日常生活でじっくり観察することが大切です。
「名探偵になったつもりで観察してみてください」とお伝えしています。
日常生活での観察ポイント
お子さんの感覚過敏に気づくためのチェックポイントをご紹介します。
こんな反応はありませんか?
聴覚(耳)のチェックポイント
- 掃除機の音を怖がって部屋から逃げ出す
- お祭りや花火大会で耳を塞いで大泣きする
- 他の子が気にしないような小さな音に「うるさい!」と反応する
触覚(触る感覚)のチェックポイント
- 洋服の特定の素材やタグを「チクチクする!」と嫌がる
- 髪を切るのを極端に嫌がって美容院で大泣きする
- 手や顔が少し汚れただけで「洗って!洗って!」と大騒ぎする
視覚(目)のチェックポイント
- 「明るすぎる!」と日差しや照明を避ける
- デパートやショッピングモールですぐに疲れる様子を見せる
- 特定の模様や動きのあるものをじっと見つめる
その他の感覚チェックポイント
- 「このネバネバ食べられない」と食感にこだわりがある
- 「この匂い気持ち悪い」と大人が気にならない香りに反応する
- ブランコやすべり台に極端な恐怖を示す
感覚統合学会の調査によると、感覚過敏の約60%は日常の観察で気づけるそうです。
保護者が「あれ?」と思う場面を集めていくと、感覚過敏のパターンが見えてくることが多いのです。
感覚過敏の評価方法|専門家へ相談するべき?
より詳細に感覚過敏を評価するためには、以下のような方法があります。
- 感覚プロファイル質問票:専門的な質問表で、お子さんの感覚特性を客観的にチェックできるものがあります
- 感覚統合の専門家による評価:作業療法士などの専門家があそびを通して評価します。楽しみながらチェックできるので、こどもも嫌がりません
- 医療機関での総合的な評価:発達小児科や児童精神科での専門的な相談も可能です
「いつ相談すべきか」の目安としては、以下のようなタイミングが考えられます。
- 感覚過敏のために日常生活がとても大変になっている
- 3歳を過ぎても感覚過敏が強くて、なかなか慣れない
- 感覚過敏に加えて、人との関わりやコミュニケーションの心配もある
- 幼稚園や保育園、学校で困ることが増えてきた
「様子を見ていいのか、相談した方がいいのか」と迷ったら、まずは地域の子育て支援センターや保健センターで気軽に相談してみるのもよいでしょう。
こどもの感覚過敏は発達障がい?役立つチェックリスト
「感覚過敏だけ」なのか「発達障がいの一部としての感覚過敏」なのか、見分けるのに役立つチェックリストを紹介します。
あくまで参考程度にしてください。
正確な判断は専門家に任せるのがベストです。
| 観察ポイント | 感覚過敏のみの可能性 | 発達障がいの可能性も考慮 |
|---|---|---|
| 感覚過敏の範囲 | 特定の感覚領域のみ | 複数の感覚領域 |
| 状況依存性 | 特定の状況でのみ現れる | 多くの状況で一貫して現れる |
| 社会性 | 社会的関わりは年齢相応 | 社会的関わりに課題がある |
| コミュニケーション | 言語発達は年齢相応 | 言語発達の遅れや特異性がある |
| 興味の範囲 | 多様な興味がある | 限定的・反復的な興味がある |
| 変化への適応 | 徐々に適応できる | 変化への適応が著しく困難 |
| 家族歴 | 家族に感覚過敏がある | 家族に発達障がいの診断がある |
「うちの子、結構当てはまるんだけど…」と心配になる方もいるかもしれませんが、チェックリストはあくまでも目安です。
一つひとつの特徴より、全体的な傾向を見ることが大切です。
成長に伴う感覚過敏の変化パターン
感覚過敏の経過パターンを知ることも重要です。
- 一時的パターン:特定の発達段階で現れ、成長とともに自然に改善する
- 変動パターン:状況やストレスに応じて強さが変動する
- 持続パターン:長期間にわたって特定の感覚過敏が継続する
国立精神・神経医療研究センターの調査によれば、発達障がいのないこどもの感覚過敏の約70%は成長に伴い軽減すると報告されています。
感覚過敏の特徴を丁寧に観察することで、発達障がいかどうかを見極める手がかりになります。
しかし、感覚過敏があること自体は発達障がいを意味するものではないことを忘れないでください。
次に、発達障がいではない感覚過敏への対応法について解説します。
発達障がいではない感覚過敏への家庭での対応法

感覚過敏は発達障がいでなくとも、適切な環境調整と理解によって大幅に改善することができます。
多くのこどもたちは、家庭での適切な対応によって感覚過敏に上手く適応していくことができます。
こどもの感覚特性に合わせた環境調整
お子さんの感覚特性に合わせて環境を調整することで、不快感を軽減することができます。
聴覚過敏への対応
- イヤーマフやノイズキャンセリングヘッドホンの使用
- 大きな音が出る前に予告する(「これから掃除機をかけるよ」など)
- 静かな「避難場所」を家の中に用意しておく
触覚過敏への対応
- タグのない衣類を選ぶ(最近はタグレス商品も増えています)
- お子さんが快適と感じる素材の衣類を選ぶ
- シャンプーのときは「泡が目に入らないシールド」を使う
視覚過敏への対応
- サングラスの使用(おしゃれアイテムとして楽しめると良いです)
- 室内の照明を調整する
- お部屋の中を視覚的にすっきりさせる
国立特別支援教育総合研究所の報告では、適切な環境調整によって感覚過敏による日常生活の困難が約50%軽減されたというデータがあります。
感覚過敏を持つこどもへの効果的なコミュニケーション
感覚過敏のあるお子さんとのコミュニケーションでは、以下のようなアプローチが効果的です。
- 感覚体験を言語化する手伝い:「その音は耳が痛くなるんだね」など、感覚体験に言葉を与える
- 前もっての予告:感覚的に挑戦する場面の前に予告する
- 選択肢の提供:「イヤーマフをつける?それとも別の部屋で待つ?」など、対処法の選択肢を提供する
- 感覚過敏への理解と共感:「わがまま」ではなく実際の不快感として理解する
適切なコミュニケーションによって、お子さん自身が自分の感覚特性を理解し、対処法を身につけることができるようになります。
日常生活での具体的なサポート方法
実際の生活場面での具体的なサポート方法をいくつか紹介します。
食事場面での工夫
- 食感の段階的な導入(最初は少量から)
- 好きな食べ物と新しい食感を組み合わせる
- 無理強いせず、少しずつ挑戦する機会を作る
学校生活での工夫
- 教師に感覚特性について伝える
- 必要に応じて静かな場所で休憩できるよう調整する
- 感覚過敏に対処するツール(イヤーマフなど)を用意する
社会活動への参加支援
- 事前に環境を下見する
- 徐々に慣れる機会を作る
- 必要に応じて感覚調整グッズを持参する
東京都教育委員会の調査では、こうした具体的サポートにより、感覚過敏のあるこどもの90%以上が社会活動に参加できるようになったと報告されています。
感覚過敏に対する段階的な慣らし方
感覚過敏に対しては、「感覚ダイエット」と呼ばれる段階的なアプローチが効果的です。
- 感覚体験の理解:どのような感覚入力が不快かを特定する
- 安全な環境での少量の感覚入力:コントロールされた環境で少しずつ挑戦する
- 徐々に感覚入力を増やす:成功体験を重ねながら徐々に刺激量を増やす
- 日常場面への般化:練習した対処法を実生活に応用する
この方法は感覚統合療法の考え方に基づいており、感覚過敏の症状を緩和するだけでなく、お子さんの自信にもつながります。
感覚過敏は発達障がいでなくても、お子さんにとって実際の不快感をもたらすものです。
適切な環境調整と段階的なアプローチで多くの場合改善していきます。
次に、感覚過敏について専門家のサポートを受ける時期と方法について解説します。
感覚過敏について専門家のサポートを受ける時期と方法

感覚過敏は発達障がいでなくても、専門家のサポートが役立つことがあります。
適切なタイミングで専門的な支援を受けることで、感覚過敏への対応が格段に効果的になるケースを数多く見てきました。
専門家に相談すべきサイン
以下のようなサインが見られる場合は、専門家への相談を検討することをお勧めします。
- 感覚過敏が日常生活や学校生活に著しい支障をきたしている
- 家庭での工夫だけでは改善が見られない
- 感覚過敏によって社会参加や学習機会が制限されている
- 感覚過敏から二次的な情緒的問題(不安や自己肯定感の低下など)が生じている
- 4歳を過ぎても感覚過敏が強く、適応できていない
小児科学会のガイドラインでは、これらの徴候が3か月以上継続する場合は専門家への相談を推奨しています。
相談は、地域の子育て支援センターや保健センターでの気軽な相談から始めても良いでしょう。
そこで必要に応じて、より専門的な機関を紹介してもらえます。
感覚統合療法など有効な支援アプローチ
感覚過敏に対する専門的アプローチにはいくつかの種類があります。
感覚統合療法
感覚統合療法は、楽しい活動を通して感覚処理能力を向上させるアプローチです。
作業療法士や理学療法士によって提供され、あそびを通して様々な感覚入力を統合する能力を高めます。
研究では、感覚統合療法を受けた感覚過敏のあるこどもの約75%に改善が見られたと報告されています。
認知行動療法的アプローチ
感覚過敏に対する認知と行動の変容を促すアプローチです。
感覚刺激に対する認知の仕方を変え、徐々に不快な刺激に慣れていく方法を学びます。
特に年長児や思春期のこどもに効果的です。
環境調整コンサルテーション
専門家が家庭や学校を訪問し、感覚過敏に配慮した環境づくりをアドバイスします。
教育機関との連携も含めた包括的な支援が特徴です。
医療機関と教育機関での支援の違い
感覚過敏に関する支援は、医療機関と教育機関でアプローチが異なります。
医療機関(発達小児科、児童精神科など)
- 医学的な評価と診断
- 感覚統合療法などの専門的治療
- 必要な場合の薬物療法(ただし感覚過敏単独では一般的ではありません)
- 保護者へのカウンセリングと指導
教育機関(幼稚園、学校、児童発達支援センターなど)
- 集団生活における環境調整
- 個別支援計画に基づくサポート
- 感覚特性に配慮した学習環境の提供
- 社会性スキルの育成
研究によると、両者の連携によって支援の効果が約40%高まることが報告されています。
保護者向けのトレーニングプログラム
感覚過敏のあるお子さんの保護者向けに、以下のようなトレーニングプログラムがあります。
- ペアレント・トレーニング:こどもの感覚特性に応じた関わり方を学ぶプログラム
- 感覚処理サポートプログラム:家庭で実践できる感覚統合活動を学ぶプログラム
- ストレス・コーピング・プログラム:保護者自身のストレス管理法を学ぶプログラム
これらのプログラムは、児童発達支援センターや医療機関で提供されています。
調査では、これらのプログラムに参加した保護者の約85%がこどもへの対応に自信を持てるようになったと報告されています。
感覚過敏は発達障がいではなくても、専門家の適切なサポートによって大きく改善する可能性があります。
お子さんの状態に応じて、適切な支援を検討してみてください。
次に、こどもの感覚過敏に関するよくある質問と回答を紹介します。
こどもの感覚過敏に関するよくある質問

感覚過敏は発達障がいではないケースが多いことを踏まえ、保護者の皆さんからよくいただく質問に専門家の立場から回答します。
長年の支援現場での経験から、よくある疑問と実践的な解決策をお伝えします。
Q: こどもの感覚過敏は、成長とともに自然に改善していくものでしょうか?
A: 多くの場合、感覚過敏は成長とともに改善していきます。
国立成育医療研究センターの追跡調査によると、発達障がいのないこどもの感覚過敏は約70〜80%が小学校高学年までに大幅に改善すると報告されています。
これは脳の感覚処理システムの成熟や、経験を通じた適応能力の向上によるものと考えられています。
ただし、改善の度合いは個人差が大きく、一部の感覚過敏は成人期まで継続することもあります。
特に強い不安や回避行動が定着している場合は、専門的なサポートが必要なこともあります。
適切な環境調整と段階的な挑戦の機会を提供することで、改善を促進することができます。
Q: こどもに感覚過敏がありますが、発達障がいの診断はありません。学校に配慮をお願いする必要はありますか?
A: お子さんの感覚過敏が学校生活に影響している場合は、診断の有無にかかわらず、学校に伝えておくことをお勧めします。
文部科学省の「合理的配慮ガイドライン」では、診断名がなくても、個々の特性に応じた配慮が推奨されています。
配慮依頼の際のポイントは以下の通りです。
- お子さんの具体的な感覚特性と、どのような場面で困難が生じるかを明確に伝える
- 家庭で効果的だった対応方法を共有する
- 無理のない範囲での配慮をお願いする
- 定期的に状況を確認し、必要に応じて調整する
多くの教育現場では、「個に応じた教育」の観点から、このような配慮に前向きに対応してくれます。
Q: きょうだいで感覚特性がまったく異なります。一人は音に敏感で、もう一人は全く気にしません。家庭でどのように対応すればよいでしょうか?
A: きょうだい間で感覚特性が異なるのはとても一般的です。
研究では、同じ家庭で育った兄弟姉妹でも約65%が異なる感覚プロファイルを持つと報告されています。
対応のポイントは以下の通りです。
- 感覚特性の違いを家族全員で理解し、「正常・異常」ではなく「個人差」として捉える
- 特性の異なるきょうだいそれぞれに適した環境を部分的に作る(例:静かな作業スペース、活動的なあそびスペース)
- きょうだい間で相互理解を促す会話を持つ
- 家族の共通ルールと個別の配慮のバランスを取る
- すべてのこどもに平等に注目と称賛を与える
「感覚特性マップ」という家族全員の感覚特性を視覚化するツールを作り、お互いの違いを尊重する取り組みも効果的です。
Q: 7歳の息子は匂いに敏感で、私が気づかないような微妙な香りの違いがわかります。この特性を将来何か活かせないかと思うのですが、どうしたらいいでしょうか?
A: 感覚過敏は「困ったこと」だけではなく、適切な環境があれば素晴らしい「強み」になる可能性があります。
国立教育政策研究所の研究でも、感覚特性を活かした教育アプローチがこどもの創造性や専門性を伸ばすと報告されています。
匂いに敏感なお子さんの場合、以下のようなアプローチがおすすめです。
- 特性を肯定的に伝える:「すごいね、君はお母さんにはわからない匂いがわかるんだね。それは特別な才能だよ」と伝える
- 関連する分野への興味を育てる:料理やお菓子作り、香水や石鹸作り、植物観察など、匂いを活かせる趣味を一緒に楽しむ
- 鋭い感覚を「観察力」として評価する:「細かいことに気づける」という点を褒める
- 自分の特性への理解を深める:「この敏感さは時々大変だけど、特別なことにも気づける。それがきみの個性だね」と伝える
将来的には、この特性を活かせる職業も多くあります。
料理人、調香師、ワインのソムリエ、香料開発者、アロマセラピストなどです。
大事なのは「この子の特性を問題としてではなく、個性として尊重する」という親の姿勢です。
そうすれば、お子さん自身も自分の感覚特性を肯定的に捉えられるようになります。
最後に、感覚過敏のこどもの実例と、親ができるサポートについて解説します。
感覚過敏の実例|長期的な視点でサポートをしよう

感覚過敏は発達障がいではないことが多く、適切なサポートがあれば、将来の可能性を広げる個性になります。
感覚過敏を抱えながら成長したこどもたちの実例
感覚過敏のあるお子さんたちが、どのように成長したのか、いくつか実例をご紹介します。
Aさんの例
幼稚園の頃、聴覚過敏がとても強くて、運動会や音楽会などの行事でいつも耳を塞いで泣いていたAさん。
小学校で音楽に興味を持ち始め、その繊細な聴覚を活かしてピアノやバイオリンの演奏が素晴らしく上達しました。
今は高校生になり、吹奏楽部で活躍しています。
「私は音に敏感だから、他の人が気づかない音色の違いがわかる」と自分の特性を肯定的に捉えています。
Bくんの例
視覚過敏があり、明るい場所や複雑な視覚環境ですぐに疲れてしまっていたBくん。
成長とともに自分の特性を理解し、上手に自己調整する力が身についてきました。
現在は大学生で芸術を専攻していて、「細部への敏感さが作品制作に活きている」と話しています。
これらの例は、国立教育研究所の追跡調査結果とも一致しています。
この調査によると、感覚過敏のあるお子さんの約75%が青年期になると自分の感覚特性を肯定的に捉えられるようになるそうです。
適切なサポートがあれば、その特性は「困ったこと」から「強み」に変わっていく可能性があるのです。
長期的な視点でサポートしよう
保護者の皆さんは、長期的視点でサポートしてあげましょう。
いくつかのポイントをお伝えします。
- 感覚特性を肯定的に捉える視点を伝える:「大変だね」だけではなく、「あなたは普通の人が気づかないことに気づける特別な力を持っているね」という捉え方を伝える
- 自分の特性と必要なサポートを伝える力を育てる:「これは苦手だから、こうしてほしい」と伝える練習をサポートする
- 敏感な感覚を活かせる活動や趣味を見つける:感覚過敏のあるお子さんが楽しめそうな活動をいろいろ試してみる
- 多様性を尊重する価値観を育む:「人はみんな違って、それでいい」という価値観を家庭内で大切にする
- 長期的な視点を持つ:「この子の感覚特性が将来どんな強みになるか」という視点で見守る
調査では、こうした肯定的アプローチを取った家庭のお子さんは自己肯定感が高く、将来に対して前向きな展望を持つ傾向が強いことがわかっています。
この記事では、「感覚過敏は必ずしも発達障がいを意味するものではない」ということをいろんな角度からお話ししてきました。
感覚過敏は多くのお子さんに見られる特性で、適切な理解とサポートがあれば十分に対応可能なものです。
発達支援の現場で働きながら、感覚過敏のあるこどもを育ててきた経験から言えるのは、この特性を「困ったこと」ではなく「その子らしさ」として捉えることの大切さです。
こどもの頃は「敏感すぎる」と悩むことも多いのですが、成長とともに自分の特性を理解し、上手に付き合っていけるようになります。
- 国立精神・神経医療研究センター (2018) 「こどもの感覚特性に関する全国調査」
- 日本感覚統合学会 (2020) 「感覚統合と発達障がいの関係性に関する最新知見」
- 東京都児童発達支援センター (2019) 「感覚過敏と発達障がいの関連性に関する研究」
- 日本発達心理学会 (2017) 「こどもの感覚プロファイルと発達支援」
- 日本自閉症学会 (2019) 「自閉スペクトラム症における感覚特性研究の動向」
- 日本小児精神医学会 (2022) 「感覚過敏と発達障がいの鑑別診断に関する臨床的考察」
- 国立成育医療研究センター (2020) 「こどもの感覚統合発達に関する研究」
- 東京大学院教育学研究科 (2018) 「感覚特性の家族間類似性に関する研究」
- 国立環境研究所 (2021) 「都市環境と児童の感覚処理能力の関連性」
- 日本小児精神医学会 (2022) 「環境変化とこどもの感覚特性に関する研究」
- 日本感覚統合学会 (2021) 「感覚特性の評価法と支援技法」
- 国立特別支援教育総合研究所 (2020) 「感覚特性に配慮した学校環境調整に関する実践研究」
- 東京都教育委員会 (2021) 「特別な配慮を要する児童生徒の支援に関する調査報告」
- 日本作業療法学会 (2019) 「感覚統合療法の効果検証に関する研究」
- 文部科学省 (2022) 「合理的配慮ガイドライン」
- 東京学芸大学 (2020) 「同胞間における感覚特性の差異に関する研究」
- 国立教育政策研究所 (2022) 「感覚特性と創造性の関連に関する研究」
- 国立教育研究所 (2021) 「感覚特性の多様性と発達過程に関する縦断的研究」
- 東京大学 (2022) 「感覚過敏の長期的予後に関する追跡研究」
- 厚生労働省 (2022) 「感覚特性と職業適性に関する調査研究」