療育で役立つ吹く遊び|口まわりの動き・呼吸のコントロールを楽しく学ぶ
 運動療育・運動遊び
運動療育・運動遊び療育における吹く遊びは、家庭でも現場でも手軽に取り入れられるあそびのひとつです。
ストローやティッシュ、シャボン玉など身近な材料を使って行えるため、特別な道具がなくても始められます。
あそびながら呼吸のコントロールや口の筋力を育てることができ、こどもの集中力や社会性、協調性といった発達面も支援できます。
この記事では、療育における吹く遊びの基本から家庭での具体例、よくある悩みの解決策まで、段階的に実践できる方法をご紹介します。
吹く遊びとは?療育における目的と効果

「吹く遊び」とは、シャボン玉や風船、ストローなどを使って息を吹く遊びのことです。
一見すると単純なあそびに見えますが、療育の現場ではこどもの成長を幅広く支える大切な活動として活用されています。楽しみながら体や心を育てることができる点が特徴です。
このあそびで育つ力は多岐にわたります。
- 口腔機能:口の力や舌の動き、唇の動きなど
- 呼吸のコントロール:息の強さや持続、方向の調整
- 言語表現:話す力や発音の安定
- 集中力:目標に向かって息を調整する注意力
- 情緒の安定:気持ちを落ち着ける力、自己調整能力
シャボン玉を吹くときに息を長く吐く練習をすることで、自然と集中力も育ちますし、風船を膨らませることで口の力や息の調整も身につきます。
さらに、公的機関の指針でもあそびを通した総合的な発達支援の重要性が示されています。
たとえば、こども家庭庁の「保育所保育指針」では、こどもが自分から環境に関わり、多様な経験を積むことで、以下の能力を育むことが推奨されています。
- 健康:呼吸や体の動きを使った運動
- 言葉:発語や言葉の練習
- 表現:声の強弱や感情を表す力
吹く遊びは、これらの能力を楽しみながら同時に育てられる、とても効果的な療育活動です。あそびの中で自然に体や心の力を伸ばせるため、家庭でも施設でも広く取り入れられています。
吹く遊びがこどもに与える発達効果

療育における吹く遊びとは、息をコントロールする動作を通じて、こどもの心と体の成長に幅広く影響を与える活動です。
息の使い方は、言葉を話す力や気持ちの安定の土台にもなります。
ここでは、吹く遊びで育つ力を具体的に見ていきましょう。
1. 口腔・呼吸機能の発達
吹く遊びは、口の周りの筋肉や呼吸の力を鍛えるのに役立ちます。
-
口腔機能の強化:唇をすぼめたり閉じたり、舌や頬を協調して動かすことで、食べる力や話す力が育ちます。
例えば、唇をしっかり閉じる力が育つと、食事中の食べこぼしが減り、舌の動きもスムーズになって飲み込みや発音の助けになります。 -
呼吸コントロール:シャボン玉をゆっくり吹いたり、ストローで物を長く吹き続けたりすると、肺活量や心肺機能が向上します。安定した息は、明瞭な発声にもつながります。
息と口の動きを意識することで、食事や発音、呼吸の力を自然に育むことができます。
2. 集中力・注意力の向上
吹く遊びでは、目標に意識を向けて行動する力が育ちます。
-
ストローで的を狙う「ストロー射的」では、息の強さや方向を調整する力が身につきます。
-
紙吹雪やティッシュを長く空中に浮かせるあそびでは、一つのことに集中して取り組む持続力が養われます。
楽しみながら取り組むことで、自然と集中力や持続力が育ちます。
3. 情緒・自己コントロールの向上
ゆっくり息を吐くことで、心を落ち着ける効果があります。
-
リラックス効果:深くゆっくり息を吐くと、体が落ち着き、不安や興奮を鎮めやすくなります。
-
感情コントロールの練習:「怒りをシャボン玉のようにフーッと吹き飛ばしてみよう」と声をかけると、破壊的でない方法で感情を発散でき、自己鎮静のスキルを体験的に学べます。
息を意識することで、こどもは感情を切り替える方法を自然に身につけられます。
4. 言語・発音のサポート
口腔と呼吸の力は、発音や話す力につながります。
-
明瞭な発音の促進:「パ・バ・マ行」の音は唇の力、「フ・ス・シ」の音は息のコントロールが必要です。吹く遊びで自然に練習できます。
-
話す力と表現力の向上:息の強さや長さを調整する経験は、声の抑揚や音量のコントロール力を育てます。
-
脳と口の連携強化:吹く動作を繰り返すことで、脳と口の神経回路が強化され、新しい言葉を覚える力や感情を伝える力も育ちます。
吹く遊びを通して、口と息の動きが、話す力や思いを伝える力の土台となります。
感覚統合療法や口の発達との関係
吹く遊びが療育で取り入れられるのには理由があります。
感覚の統合や口の発達に関する研究から、その効果がしっかり裏付けられており、療育の現場でも活用されています。
感覚統合療法との関わり
感覚統合とは、目・耳・体・口などから入ってくる情報を脳で整理し、スムーズに使えるようにする力のことです。発達に課題があるこどもの中には、この処理が少し苦手な子もいます。
吹く遊びは、自然にこの感覚統合を練習できるあそびです。
・口や唇、舌への刺激
息を吹いたり、ストローを口に挟んだりすることで、口の周りの筋肉や動きを脳がしっかり感じます。
→ 口の感覚が敏感すぎたり鈍すぎたりするこどもにも、ちょうど良い刺激になります。
・いろいろな感覚を同時に使う
例えば、ストローで的を狙うあそびでは、
- 目で的を見る(視覚)
- 体の姿勢を整える(体の感覚)
- 息を吹きかける(触覚・筋肉感覚)
このように、複数の感覚を同時に使います。
この体験自体が、脳の感覚統合を鍛えるトレーニングになるのです。
口の発達とグレーゾーンのこどもへの応用
口の使い方(口腔機能)は、こどもの健康や発達にとても重要です。話す力や食べる力に関わり、日常生活や社会参加を支える役割があります。
特に、発達障がいの診断はついていないけれど、口がポカンと開いている、発音が少し不明瞭といったこどもには、吹く遊びが役立ちます。
年齢・発達段階別の「吹く遊び」療育の特徴

療育における吹く遊びは、こどもの発達段階に合わせてあそび方を工夫すると、より効果的に成長をサポートできます。
ここでは、文部科学省や厚生労働省の発達の目安を参考に、年齢ごとのあそびの例とねらいを紹介します。
2~3歳:息を使うあそびの導入
この年齢のこどもは、体の基本的な動きが育ち、簡単な指示も理解できるようになります。あそびの中心は、「息を吹くと何かが動く」という楽しさの発見です。
あそびの例
- シャボン玉:吹くと玉が飛ぶ様子を楽しむ。大人が見せるだけでも効果があります。
- ティッシュ・綿玉飛ばし:テーブルの上に置いた軽いティッシュや綿玉を「フーッ」と吹いて動かす。
- 風車:息を吹くとクルクル回る様子を楽しむ。
ねらい
- 息を「吹く」という感覚を楽しむ
- 口から息を出す感覚を掴む
- 唇や頬の筋肉を使う練習、簡単な因果関係の理解
4~6歳:息を長く・方向を意識するあそび
この年齢になると、体の動きをより上手にコントロールでき、簡単なルールのあるあそびにも参加できるようになります。息の強さや長さ、方向を意識する力を育てるあそびがおすすめです。
あそびの例
- 吹き戻し(ピロピロ笛):「3つ数えるまで伸ばしてみよう」といった目標を設定
- ストローサッカー:ストローで紙やピンポン玉を吹いてゴールに入れる
- 水あそびでの船レース:軽い船を息で吹いて進ませる
ねらい
- 息を一定時間持続して吹く力
- 狙った方向に息を当てるコントロール
- 簡単なルールの理解
小学生:音や協力ゲームでステップアップ
小学生になると、複雑なルール理解や社会性、指先の巧緻性が育ちます。リコーダーやハーモニカ、チームでのゲームを通して、呼吸のコントロールだけでなく協力する力や順番を守る力も伸ばせます。
あそびの例
- リコーダー・ハーモニカ:息と指の使い方を組み合わせ、音を出す楽しさを学ぶ
- ストローリレー:ストローで紙片を吸い上げ、落とさず次の人に渡すチームゲーム
- ストロー射的:的を倒して点数を競い、集中力と競争心を養う
ねらい
- 複雑な呼吸のコントロール(音階や強弱の調整)
- 指先の協調性
- 社会性・協力・ルールを守る力
年齢別あそびのまとめ表
| 年齢 | あそびの例 | 期待される主な効果 |
|---|---|---|
| 2~3歳 | シャボン玉、ティッシュ飛ばし、風車 | 息を吹く体験、口唇筋肉の意識づけ、因果関係の理解 |
| 4~6歳 | ストローサッカー、吹き戻し、水に浮かべた船 | 息の強弱・方向のコントロール、持続的呼気、簡単なルール理解 |
| 小学生 | リコーダー、ハーモニカ、ストローリレー、ストロー射的 | 複雑な呼吸コントロール、指先との協調、協力・社会性、ルール遵守 |
あそびをただの時間つぶしにするのではなく、発達を意識した活動として取り入れることで、こどもは楽しみながらさまざまな力を伸ばせます。
吹く遊びの基本ルールと安全ポイント

吹く遊びは手軽に始められるあそびですが、誤飲や衛生管理は、児童福祉施設や公的機関でも繰り返し注意が呼びかけられています。
こどもが安全に、そして楽しく取り組むためには、いくつかの基本ルールと注意点を守ることが大切です。
ここでは、家庭や施設で吹く遊びを導入する際の具体的なポイントを解説します。
「吹く遊び」の基本ルール
まず、あそび方の基本として意識したいのは、息の強さや方向、距離の調整です。
あそびを始めるときは、まず優しく吹くことからスタートし、慣れてきたら少しずつ強く、長く吹けるように段階を踏みます。
また、こどもが息を吹きかける対象を意識できるよう、大きくて近い的から始め、少しずつ小さくて遠い的に挑戦することで、自然に難易度を上げることができます。
道具の扱い方にも注意が必要です。
小さな部品を口に入れてしまうリスクがあるため、3歳未満のこどもが遊ぶ場合は、トイレットペーパーの芯(直径約4cm)より小さい部品は使用しないようにしましょう。
また、ストローや吹き戻し、笛などの道具はひび割れや破損、部品の緩みがないかを事前に確認してください。
破損した道具は、口の中を傷つけたり誤飲の原因になるため、すぐに取り替えます。
安全な道具を選ぶ際は、「STマーク」のある製品を選ぶと安心です。
「STマーク」は、日本玩具協会が定めた安全基準に適合したおもちゃに付けられるマークです。
・有害物質が使用されていないか
・部品が小さすぎて誤飲の危険がないか
・刃物や尖った部分がないか
など、こどもが安全に遊べるかどうかの基準をクリアした証です。
時間・頻度の目安
活動時間や頻度も、こどもの発達に合わせて調整することが重要です。
1回のあそびは5〜10分程度を目安に、
初めての場合や集中力が続きにくいこどもは2〜3分から始めましょう。
長時間行うよりも、短いセッションを1日に数回、あそびの中に自然に取り入れる方が効果的です。
最も大切なのは、こどもの様子を観察し、飽きていたり疲れていたり、嫌がっているサインがあれば、目標時間に達していなくても中断する柔軟性を持つことです。
安全・衛生面の注意
衛生面や感染症対策も欠かせません。
口に触れる道具はできるだけ個人専用とし、共有する場合は洗浄・消毒を徹底します。
洗浄は食器用洗剤と流水で汚れを落とし、必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム溶液やアルコールで消毒します。
遊ぶ際は歩き回らず座った状態で行い、大人がそばで監督することで、目や喉を突く事故を防ぎます。
安全管理のチェックリスト
安全管理のポイントを簡単に確認できるチェックリストをご用意しました。
あそびを始める前に毎回確認することで、こどもが安全に楽しく取り組める環境を整えられます。
【道具の準備と安全確認】
- 破損・緩みの確認
- 誤飲サイズの確認(3歳未満のこどもが口に入れる可能性のある部品はないか)
- 衛生状態の確認(洗浄・消毒済みか)
【環境の準備】
- 周囲に危険な物がないか
- こどもが安定して座れる場所か
【あそびの計画】
- 今日のあそびの目的は何か(例:長く吹く、的を狙う)
- 時間は短く設定したか(目安:5〜10分)
- 中断の目安を考えているか(疲れや嫌がりサインがあれば終了)
家庭でできる吹く遊びの療育の具体例

家庭での日常的な関わりがこどもの発達を大きく支えます。
ここでは、特別な道具を必要とせず、身近な材料で今日からすぐに実践できる吹く遊びの療育の具体例をご紹介します。
簡単な道具でできるあそび
家庭にあるストローや紙、ペットボトルなどを使って手軽に始められます。
1. ストローで紙吹雪・綿玉飛ばし
テーブルの上に細かくちぎった色紙やティッシュ、綿玉を置き、ストローで息を吹いて飛ばします。
ゴール地点を決めて「レース」にしたり、絵の上に紙吹雪を置いて「宝探し」のように楽しむこともできます。
2. 吹き戻し(ピロピロ笛)や風船あそび
吹き戻しは、息を吹くと紙の筒が伸び、息を止めると戻るシンプルなおもちゃです。
できるだけ長く伸ばし続ける、リズムに合わせて伸縮させるなど、持続的な呼気の練習に適しています。
また、風船あそびは、膨らませる行為自体が強い呼気と口周囲筋を必要とするため、より高度なトレーニングになります。
3. ペットボトルで的当て
空のペットボトルや軽い紙コップを並べ、ストローで作った吹き矢や丸めたティッシュを吹いて倒すゲームです。
家庭でできる吹く遊び一覧(難易度・効果別)
| あそびの種類 | 難易度 | 主な効果 | 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ティッシュ・綿玉飛ばし | ★☆☆ (易しい) | 息を吹く感覚の習得、呼気の方向づけ | ティッシュ、綿玉 |
| シャボン玉 | ★☆☆ (易しい) | 持続的で優しい呼気の練習、視覚的追跡 | シャボン玉液 |
| 吹き戻し | ★★☆ (普通) | 持続的な呼気のコントロール、口唇の筋力 | 吹き戻し |
| ストローで的当て | ★★☆ (普通) | 呼気の強さと方向のコントロール、集中力 | ストロー、紙コップ等 |
| 風船膨らまし | ★★★ (難しい) | 強い呼気、口腔周囲筋・腹筋の強化 | 風船 |
導入のコツ・こどもが嫌がるときの工夫
吹く遊びは、楽しいあそびですが、こどもによっては最初は興味を示さなかったり、うまくできずに嫌がることもあります。そんなときは、いくつかの工夫で意欲を引き出すことができます。
- ゲーム形式や競争形式にする
「どっちが遠くまで飛ばせるか」「30秒でいくつ的を倒せるか」など、競争やゲーム要素を加えると意欲が高まります。 - 小さな成功体験を褒める
少しでもできたことを具体的に褒めることで、達成感が次への挑戦につながります。 - 大人が楽しそうに見せる
保護者が楽しんでいる姿を見せると、こどもも興味を持ちやすくなります。 - 短時間で区切る
「あと3回吹いたらおしまい」など、終わりを明確に示すと集中力が持続しやすくなります。
家庭で出来る「吹く遊び」療育の応用例
家庭で取り入れる際は、いきなり難しいことに挑戦するのではなく、段階を踏むのがポイントです。最初は「長く吹く」「強く吹く」といった基本から始め、慣れてきたらコントロールや音あそびへとステップアップしていくと無理なく楽しめます。
それぞれのステップはあそびながら自然に発達を促すことができ、達成感や自信にもつながります。
こどもの様子を見ながら、「今日はここまで」「次はこのあそび」と少しずつ進めていくと効果的です。
ステップ1:長く・強く吹く
- 吹き戻しの時間を少しずつ長くする
- 軽い紙ではなく、少し重いピンポン玉で飛ばす
- シャボン玉を1回の息でできるだけたくさん作る
ステップ2:方向や強弱をコントロール
- ストローサッカーでゴール位置や障がい物を変える
- 的当ての距離を少しずつ遠くする
- シャボン玉で「小さい玉」「大きい玉」と吹き分ける練習
ステップ3:音を出すあそびに挑戦
- リコーダーやハーモニカなど、息で音を出す楽器に触れる
- ストローの先を少し潰して切り込みを入れると簡易リード笛になり、息の強さで音の高さを変えられる
家庭でのあそびは、療育の成果を日常生活に広げる重要なステップです。保護者があそびの目的を理解し、こどものペースに合わせて楽しみながら取り組むことで、こどもの「できる」を確実に増やすことができます。
よくある悩みと解決策 Q&A
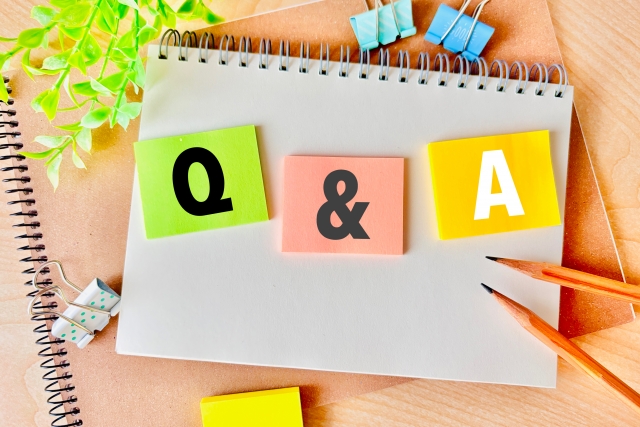
吹く遊びを家庭や療育現場で実践する中で、保護者や支援者が直面しやすい悩みと解決策をQ&A形式でまとめました。
こどもの反応に合わせて柔軟に対応するためのヒントとしてご活用ください。
Q1:すぐに飽きてしまったり、集中力が続かなかったりする場合はどうすればいいですか?
A1:あそびの「量」と「質」を見直しましょう。
-
時間を短くする: まずは「1回吹くだけ」「10数えるまで」など、ごく短い時間から始めます。こどもが「もっとやりたい」と思うくらいで切り上げることが、次への意欲を持続させるコツです。活動時間は5分でも長すぎる場合がありますので、こどもの集中力に合わせて1~2分程度に設定し直してみましょう。
-
報酬や達成感を設定する: 「的を倒せたらシールを1枚貼る」「全部できたら好きなおやつ」といった魅力的なご褒美を用意したり、活動の成果を目に見える形(倒した的の数、シールの数など)で示すことで達成感を得やすくなります。
-
あそびのバリエーションを増やす: 同じ「吹く」という活動でも、使う道具やルールを変えるだけで、こどもの興味を引きやすくなります。ストロー、シャボン玉、的当てゲームなど複数の選択肢を用意し、その日の気分に合わせて選ばせると効果的です。
Q2:専用のおもちゃや道具がない場合、何かで代用できますか?
A2:家庭にある身近なもので十分楽しめます。
・紙類
- ティッシュペーパー: 1枚に剥がしてフワフワと飛ばすだけで、優しい息遣いの練習になります。
- 折り紙・色紙: 細かくちぎって紙吹雪にしたり、動物の形に切って「生き物レース」に利用できます。
- トイレットペーパーの芯: 息で転がすターゲットや、メガホンのようにして声を出すあそびに使えます。
・プラスチック類
- ストロー: 飲み物用で十分代用可能。吹き矢や笛にも使えます。
- ペットボトル・紙コップ: 的当てゲームの的として最適。水の量で重さを調整できます。
- 食品トレー: 水に浮かべて「船」として吹く遊びに活用可能。
・その他
- 綿や羽: 軽くて飛びやすく、息を吹く楽しさを実感できます。
- ピンポン玉: ステップアップ用に少し力が必要な素材として利用できます。
・ストロー吹き矢: 太めのストローの一端をテープで塞ぎ、細いストローを差し込むだけで安全な吹き矢が作れます。
・ストロー笛: 先端をV字にカットしたり平らに潰して角を落とすだけで、息を吹くと音が出る簡単な笛になります。
Q3:口の力が弱くて、うまく吹けない場合はどうすればいいですか?
A3:小さな段階に分けて、成功体験を積み重ねましょう。
・吹く練習を小分けにする: 「吹く」という動作そのものの前段階から始めます。
- 唇を閉じる練習: 「んー」と口を閉じて声を出す、ストローを挟んで数秒キープするなど口輪筋を意識する。
- 息を出す練習: ろうそくの火を消す、手のひらに「ハーッ」と吹きかけるなど、目標物がなくてもできる息出し練習。
・軽い・抵抗の少ない道具から始める
- シャボン玉: 弱い息でも玉が作れ、成功体験を得やすい。
- 軽いティッシュや羽: ほんの少しの息でも動くため、因果関係が理解しやすい。
- 太めのストロー: 細いストローより息が通りやすく、弱い力でも吹きやすい。
・段階的に練習する
難易度を下げて「できた!」という経験を重ねます。例えば、ストローでうまく吹けない場合は、ティッシュ飛ばしに戻すなど柔軟に計画を調整します。口腔機能の発達には個人差があるため、焦らずこどものペースに寄り添う姿勢が大切です。





