発達障がいの子が気持ちの切り替えができないのはなぜ?脳の仕組みを知ろう
 発達障害
発達障害「いつまでもゲームをやめられない…」
「さっき怒られたことを、ずっと引きずってメソメソしている…」
「次の予定があるのに、今やっていることから一向に離れられない…」
こどものこんな姿を見て、「どうして気持ちを切り替えられないの?」「わがままなだけ?」と、心を悩ませている保護者の方も多いのではないでしょうか。
あるいは、ご自身が仕事でのミスをいつまでも引きずってしまったり、一度考え始めると頭から離れなくなったりして、行きづらさを感じている方もいらっしゃるかもしれません。
でも、その「気持ちの切り替えの苦手さ」は、本人の怠けや、わがままが原因ではないこともあります。
発達障がいの特性による「感情をコントロールする力」に関わる、脳の仕組みから来ています。
この記事では、なぜ発達障がいがあると気持ちの切り替えができないのか、その理由を解説し、今日からできる具体的なサポート方法まで、一緒に考えていきたいと思います!
なぜ発達障がいだと気持ちの切り替えが難しいのか

発達障がいだと気持ちの切り替えが難しいのは、本人の「気合い」や「やる気」の問題ではなく、脳の機能的な特徴が関係していることが分かっています。
特に「ワーキングメモリ」と「扁桃体」という2つの部分の働きが鍵を握っています。
ワーキングメモリと扁桃体の関係をやさしく解説
少し専門的な話になりますが、私たちの脳には「ワーキングメモリ」という、情報を一時的に記憶し、同時に処理するための機能があります。
これはよく「脳のメモ帳」に例えられます。
このメモ帳が広いと、たくさんの情報を一度に書き込んで、複雑な作業もスムーズに行えます。
一方、脳の奥には「扁桃体(へんとうたい)」という、快・不快といった原始的な感情を生み出す部分があります。
こちらは「感情のアクセル」のような役割です。
楽しいことがあるとアクセルを踏み込み、嫌なことがあると急ブレーキをかけるように、私たちの感情を動かします。
発達障がいのある方は、この「ワーキングメモリ(脳のメモ帳)」の容量が比較的小さい傾向にあると言われています。
メモ帳が小さいと、一度にたくさんの情報を処理するのが苦手になります。
では、気持ちの切り替えとどう関係するのでしょうか?
例えば、楽しいことに夢中になっているとき、「感情のアクセル」である扁桃体は興奮状態にあります。
ここで、「もうやめなさい」と言われると、「ゲームを中断して、次の行動(宿題など)に移る」という指示を理解し、興奮した感情を抑え、行動に切り替える…という、いくつもの作業を行う必要があります。
ワーキングメモリの容量が十分にあれば、これらの情報を処理し、「わかった、やめよう」と理性的に感情をコントロールできます。
しかし、容量が少ないと「やめなさい」という指示を処理している間に扁桃体の「もっとやりたい!」という強い感情にメモ帳が埋め尽くされてしまいます。
その結果、脳がフリーズしてしまい、行動を切り替えられなくなってしまうのです。
これは決して反抗しているわけではなく、脳が一度に処理できる情報量を超えてしまい、パニックに近い状態になっている、と理解してあげることが大切です。
疲労やストレスなど環境要因の影響も大きい
脳の特性に加えて、環境要因も気持ちの切り替えに大きく影響します。
発達障がいのある方は、ない方に比べて疲れやすかったり、ストレスを感じやすかったりする傾向があります。
| 環境要因 | |
| 感覚過敏 | 周りの音や光、人の視線などが過剰な刺激となり、知らず知らずのうちにエネルギーを消費している。 |
| 睡眠の問題 | 寝付きが悪い、夜中に何度も目が覚めるなど、質の良い睡眠がとれず、常に疲労感が残っている。 |
| 環境の変化 | 予測できない出来事や、いつもと違う状況が大きなストレスになる。 |
心や身体が疲れていると、誰でもイライラしやすくなったり、気持ちのコントロールが難しくなったりしますよね。
発達障がいのある方の場合、元々の脳の特性にこれらの環境要因が重なることで、さらに気持ちの切り替えが難しくなり、癇癪やパニックにつながってしまうことがあります。
発達障がいで気持ちの切り替えができないときによくある場面
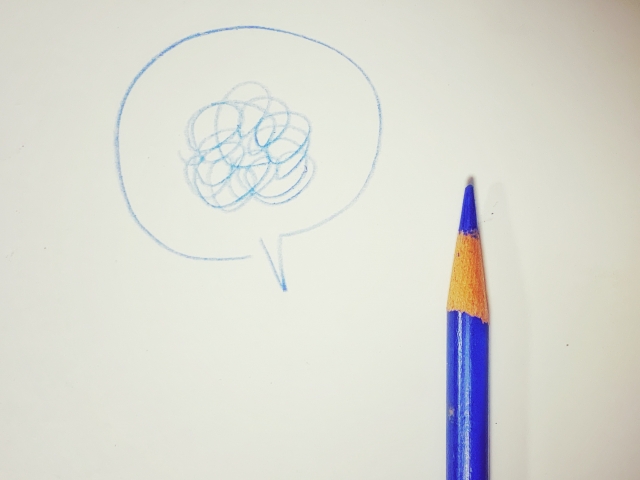
発達障がいの方の気持ちの切り替えの難しさは、生活の様々な場面で現れます。
ここでは、学校・職場・家庭の3つのシーンで具体的な例を見てきましょう。
学校での例(切り替えられず授業に戻れない)
休み時間に友達と夢中になって遊んでいたA君。
授業開始のチャイムが鳴りましたが、興奮が冷めず、なかなか席に着けません。
先生に注意されても、頭の中はまだ遊びの続きでいっぱいです。
無理やり席に着かされても、気持ちが授業モードに切り替わらず、そわそわしたり、前の時間のことを引きずってしまって、内容が頭に入ってきません。
【このときの脳の状態は?】
楽しい遊びによって、脳の「感情のアクセル」役である扁桃体がフル回転し、興奮状態にあります。
その強い「楽しい!」という感情が、情報を整理する「脳のメモ帳」(ワーキングメモリ)を埋め尽くしてしまっている状態です。
そのため、「授業に集中する」という新しい指示を処理できず、行動を切り替えられないのです。
職場での例(ミスを引きずって集中できない)
Bさんは、上司に書類のミスを指摘されました。
すぐに修正すれば済むことなのですが、「また失敗してしまった」という思いが頭の中をぐるぐる回り、気分が落ち込んでしまいます。
気持ちを切り替えて次の仕事に取りかかろうとしても、先ほどのミスのことばかり気になって集中できません。
結果的に、他の仕事の効率も落ちてしまい、さらに自己嫌悪に陥るという悪循環になってしまいます。
【このときの脳の状態は?】
ミスというネガティブな出来事によって、脳の「警報装置」が作動し、強い不安や恐怖を感じています。
この強い感情がワーキングメモリを占領し、思考の切り替えがうまく機能しなくなります。
一つの考えに固執してしまう「過集中」という特性が、ネガティブな方向へ働いてしまっている状態です。
家庭での例(癇癪・こだわりで予定が進まない)
夕方、公園で遊んでいたCちゃん。
「もうお家に帰るよ」とお母さんが声をかけましたが、「まだ遊びたい!」と一点張りで、その場から動きません。
無理に連れて帰ろうとすると、大声で泣き叫び、癇癪を起こしてしまいます。
Cちゃんの中では「楽しい遊びを中断される」という俯瞰な感情が爆発してしまい、お風呂やご飯といった次の予定に気持ちを切り替えることができなくなっているのです。
【このときの脳の状態は?】
こどもの脳はまだ発達途中であり、感情をコントロールする前頭前野の働きが未熟です。
楽しい活動を中断されることへの不快感が、感情のアクセル(扁桃体)を暴走させ、脳全体が感情の洪水に飲み込まれているような状態です。
理性的な思考ができなくなり、感情をそのままで表現してしまいます。
発達障がいでもできる!気持ちの切り替えを助ける具体的な方法

発達障がいの気持ちの切り替えは、練習や工夫によって少しずつ上手にしていくことができます。
ここでは、家庭や支援の現場で今日からすぐに取り入れられる具体的な方法をご紹介します。
こどもへの支援方法(切り替え予告・視覚カード・報酬システム)
こどもへの支援で最も大切なのは、「見通しを持たせてあげること」です。
いきなり「終わり!」と言われるとパニックになってしまうため、心の準備をさせてあげましょう。
| 支援方法 | 具体的なやり方 | ポイント・効果 |
| 切り替えの予告 | ・「長い針が6になったらおしまいね」
・「あと3回滑り台をやったら帰ろうね」 ・タイマーや砂時計を見せて、音や見た目で終わりを知らせる |
時間や回数で終わりの見通しを立てることで、心の準備ができ、唐突な中断によるパニックを防ぎます。 |
| 視覚支援カード | ・「あそび」→「おかたづけ」→「ごはん」のように、活動の順番をイラストや写真カードで示す | 言葉の指示よりも、目で見て次の行動を理解できるため、先の見通しが立ちやすく、安心して行動を移せます。 |
| ごほうびシステム | ・「これが終わったら、好きなおやつを食べようね」と、切り替えの後に楽しい予定を用意する
・ポイントを貯めて好きなものと交換する |
切り替えた先に楽しみがあることを明確にすることで、行動への意欲(モチベーション)を引き出し、前向きな切り替えを促します。 |
習慣づける方法(コーピングリスト・スケジュール調整)
自分自身の気持ちの切り替えが苦手だと感じる方が、「コーピングリスト」の作成をおすすめします。
コーピングとは「ストレスへの対処法」のことです。
自分がどんな時に気持ちが落ち込み、どうすれば回復するかを書き出してみましょう。
コーピングリストの例
- イライラしたら冷たい水を飲む
- 悲しい気持ちになったら、好きな音楽を聴く
- 疲れたら、5分だけ目を閉じて休む
- 好きなアロマの香りを嗅ぐ
- ふかふかのタオルに顔をうずめる
大切なのは、「〇〇してはいけない」ではなく「〇〇をしよう」というポジティブな行動をリストアップすることです。
リストをスマホの待ち受けにしたり、手帳に貼ったりして、いつでも見返せるようにしておきましょう。
また、疲れやストレスが切り替えを難しくするため、スケジュール管理も重要です。
予定を詰め込みすぎず、意識的に休息時間を確保したり、苦手な作業の後には得意な作業を入れたりするなど、自分にあったペースを見つけることが心の安定につながります。
親や支援者ができる声かけの工夫
気持ちを切り替えられない本人を前にすると、つい「早くしなさい!」「どうしてできないの!」と感情的に叱ってしまいがちです。
しかし、それでは本人の不安を煽るだけで逆効果です。
大切なのは、まず本人の気持ちに寄り添い、共感することです。
そして次にどうすればいいかを具体的で分かりやすい言葉で伝えることです。
| 悪い声かけの例 | 良い声かけの例 |
| 「いつまで泣いてるの!いい加減にしなさい!」 | 「そっか、終わりにするのが嫌だったんだね。悲しい気持ちになったね。じゃあ、まず顔を洗ってさっぱりしようか」 |
| 「何回言ったらわかるの!早く片付けて!」」 | 「ブロック楽しかったね。じゃあ、赤いブロックを3つ、お片付けボックスに入れてみようか」 |
| どうして集中できないの?しっかりしなさい!」 | 「疲れてきたかな?5分休憩して、温かいお茶を飲んでから、もう一度やってみようか」 |
| 「なんで準備しないの!置いていくよ!」 | 「そっか、まだ遊びたいんだね。じゃあ、どっちの靴を履いていくか一緒に選ぼうか」 |
否定的な言葉ではなく、「そうだね」と一度受け止めることが大切です。
そして、「まず〇〇しよう」と次にやるべき具体的な行動(スモールステップ)を一つだけ示すことで、本人は落ち着きを取り戻し、次の行動へ移りやすくなります。
セルフチェックと専門機関の活用で悪循環を防ぐ

「うちの子、もしかして…」「自分のこの生きづらさは…」と感じたら、一人で抱え込まずに、客観的に状況を把握し、専門機関に相談することが大切です。
それは、適切な支援につなげるだけでなく、うつ病や不安障害といった二次障害を防ぐためにも非常に重要です。
発達障がいの気持ちの切り替えの苦手さは、本人と周囲の工夫や理解によって、和らげていくことができます。
気持ちの切り替えができないときの簡易チェックリスト
まず、現状を把握するために、以下の項目をチェックしてみましょう。(これは医学的な診断ではありません。あくまでも、気づきのための目安です)
- 好きなことに夢中になると、声をかけてもなかなかやめられない
- 予定の変更や急な出来事があると、混乱したり怒ったりする
- 嫌なことがあると、そのことで頭がいっぱいになり、他のことが手につかない
- 負けることが極端に嫌いで、ゲームなどで負けるとひどく落ち込む、または怒る
- 自分の思い通りにならないと、大声を出したり、物を投げたりすることがある
- 授業や仕事の切り替えがうまくいかず、ぼーっとしてしまうことがある
- 終わったことをいつまでも気にして、くよくよ考えてしまう
- 「次は〇〇するよ」と前もって伝えても、スムーズに行動できないことが多い
いくつかの項目に当てはまる場合は、専門家への相談を検討してみるのも一つの方法です。
発達障がい者支援センター・カウンセリングの活用
もし悩んだら、以下のような専門機関に相談することができます。
相談することで、具体的なアドバイスがもらえたり、利用できる福祉サービスの情報を提供してもらえたりします。
| 相談機関 | 主な役割・できること |
| 発達障がい者支援センター | 各都道府県・指定都市に設置されている総合的な相談窓口。本人や家族からの様々な相談に応じ、助言や情報提供、関係機関との連携を行ってくれます。 |
| 市町村の保健センター・子育て支援センター | 身近な地域での相談窓口。特にこどもの発達に関する相談に強く、保健師や相談員が話を聞いてくれます。 |
| 医療機関(児童精神科、精神科など) | 医師による診断や、必要に応じた薬物療法、医学的な観点からのアドバイス、カウンセリングなどを受けることができます。 |
| カウンセリングルーム | 臨床心理士などのカウンセラーによる専門的なカウンセリングが受けられます。本人の困りごとの整理や、家族の関わり方についてじっくり相談ができます。 |
二次障害を防ぐために早めに相談する重要性
気持ちの切り替えがうまくできないことで、周囲から何度も叱られたり、失敗体験を繰り返したりすると、本人は「自分はダメな人間なんだ」という自己否定感を強めてしまいます。
こうした状態が続くと、自身を失い、うつ病や不安障害、不登校や引きこもりといった「二次障害」につながる危険性があります。
大切なのは、問題が深刻になる前に、できるだけ早い段階で専門家に相談し、適切なサポートを受けることです。
「相談するのは大げさかもしれな」と思う必要はありません。
専門家の力を借りることは、本人と家族が笑顔で過ごせる未来への大切な一歩となるはずです。
このように、発達障がいの気持ちの切り替えの苦手さは、本人と周囲の工夫や理解によって、和らげていくことができます。





