ぬいぐるみが好き=発達障がい?こどもの行動の意味を知ろう
「うちの子はぬいぐるみが好きで手放せない…。これって発達障が...
発達障がいのさまざまな特性が、どのように現れるかを一目で確認できます。
下のチャートで、ASD・ADHD・SLDの典型的な特性を見比べてみましょう。
※このグラフは典型的な特性の傾向を示した例です。実際には個人差が非常に大きく、同じ診断名でも現れ方は人それぞれ異なります。
社会的なコミュニケーションや相互作用の難しさ、限定された反復的な行動や興味が特徴です。個人差が大きいので、あくまで参考としてご覧ください。
ASDの感覚特性は、単純に「敏感」か「鈍感」かの二択ではありません。一人の人が、状況や感覚の種類によって「過敏さ」と「鈍さ」を併せ持つことが大きな特徴です。例えば、「聴覚はとても敏感だが、痛覚は鈍い」「特定の音には苦痛を感じるのに、人の呼びかけには気づきにくい」といったように、感覚のアンバランスさが現れます。
※これらの感覚特性は、すべてのASDの方に当てはまるわけではなく、あくまで一例です。個人によって感じ方は大きく異なります。
「不注意」と「多動・衝動性」が主な特徴です。集中が続きにくかったり、そわそわして落ち着かない行動が見られることがあります。
特性の現れ方によって、3つのタイプに分けられます。
知的発達に遅れはないものの、「読む・書く・計算」など特定の能力に困難があります。本人の努力不足ではなく、適切な方法でサポート可能です。
文字と音を結びつけるのが難しく、文章をスムーズに読めないことがあります。
文字の形を思い出せない、鏡文字になりやすい、文章構成が難しい場合があります。
数の概念理解や文章題の計算が難しい場合があります。
発達障がいという言葉を耳にする機会は増えています。
「自分のこどもがそうかもしれない」「家族や身近な人に当てはまるかも」と不安を感じる保護者も少なくありません。
発達障がいは、医学的には「神経発達症(Neurodevelopmental Disorders)」と呼ばれる診断群に含まれます。
これは、生まれつきの脳の発達に関わる障害であり、親の育て方や本人の努力不足が原因ではありません。
診断は、世界で広く使われる二つの基準に基づいて行われます。
・アメリカ精神医学会(APA)『DSM-5』
・世界保健機関(WHO)『ICD-11』
これらの基準では、個人の特性が日常生活や社会生活にどのくらい影響しているかを評価します。
たとえば・・・
ASD(自閉スペクトラム症):社会的コミュニケーションの難しさや、決まった行動・興味に偏りがある
ADHD(注意欠如・多動症):不注意、多動、衝動性などが持続的に見られる
最近では、診断の名称や分類が見直され、「広汎性発達障がい」から「自閉スペクトラム症」に統合されました。
この変更は、状態を「別々の病気」と考えるのではなく、特性の現れ方や重症度に幅がある一つの状態(スペクトラム)として捉えることを意味します。
スペクトラムとは、「幅広い範囲」などの意味を持つ単語です。
発達障がいの核心は、脳の働きに「偏り」や「アンバランス」があることです。
これは、ある能力は平均より低いのに、別の能力は高い、という発達の凸凹として現れます。
代表的な脳の働きの偏りには、次の3つがあります。
実行機能(計画・管理能力)
・目標を立てて、段取りよく行動する力
・実行機能が弱いと、物事の順序立てや自己管理が苦手になり、衝動を抑えにくくなる
報酬系機能(やる気や満足感に関わる力)
・すぐに得られる報酬を優先し、長期的な努力が苦手になることがある
中枢性統合(情報をまとめる力)
・全体像を把握して判断する力
・中枢性統合が弱いと、細かい部分ばかりに気が行き、相手の意図や場の空気を読みづらくなる
脳の働き方が人それぞれ違うため、こどもによって得意なこと・苦手なことの差がとても大きくなります。
これらの理由により、全ての子に同じ方法で支援しても効果が出にくいことがあります。
発達障がいは、生まれつきの脳の特性に起因するもので、後天的に発症するものではありません。
多くの場合、乳幼児期からその兆候は見られます。
ただし、成人になって初めて診断される人も増えています。
これは「後天的に発症した」わけではなく、こども時代は目立たなかった特性や、周囲のサポートによって困難が隠れていただけです。
大人になると、社会や生活環境の複雑さにより、困難が顕在化することがあります。
誤解①育て方が原因
発達障がいは脳の機能の違いによるもので、親の愛情不足やしつけが原因ではありません。
保護者が自分を責める必要はなく、理解と支援が大切です。
これはとても大切なことなので、この後も繰り返しお伝えしていきます。
誤解②個性と混同されやすい
発達障がいの人にはユニークな才能や視点がありますが、「個性」だけで片付けることには注意が必要です。
医学的に「障害」と呼ばれるのは、その特性がその子にとって、日常生活や社会生活に著しい困難をもたらし、支援が必要な状態だからです。
大切なのは、個性を尊重しつつ、困難(お子さんが困っていること)に対しては適切な理解と支援を行うことです。
発達障がいは、その特性の現れ方によって、主に「自閉スペクトラム症(ASD)」「注意欠如・多動症(ADHD)」「学習障害(LD)」の3つのタイプに分類されます 。
ただし、これらは明確に分かれているわけではなく、複数の特性を併せ持つことも少なくありません。ここでは、それぞれの主な特徴を解説します。
ASDは、自閉スペクトラム症の略で、社会的なコミュニケーションや対人関係に特徴的な困難が見られる発達障がいです。
以前は、自閉症の中でも軽度のものを「アスペルガー症候群」と呼んでいましたが、現在は*「自閉スペクトラム症」という一つの診断名に統合されています。
*DSM-5(診断・統計マニュアル第5版)やICD-11(国際疾病分類第11版)の診断基準
つまり、アスペルガー症候群という名称は現在の診断上は使われず、軽度から重度まで幅広い状態を「ASD」として捉えるのが基本です。
ASDの特性は個人差が非常に大きく、同じ診断でも困難の現れ方は人によって異なります。
ADHDは、注意欠如・多動症の略で、主に「不注意」と「多動性・衝動性」の二つの症状群によって特徴づけられる発達障がいです。
人によっては両方の症状が現れることもありますが、どちらか一方が強く現れる場合もあります。このため、症状の出方は個人差が大きく、日常生活での困りごともそれぞれ異なります。
ADHDの方は、日常生活で物を「ぽん!」と置いて立ち去ってしまうことがあり、自分では置き場所の記憶が全くないといいます。こうした失敗が重なることで、「自分はだらしない」「何度も同じ失敗をするダメな人間だ」と深く自己評価を傷つけてしまうこともあります。
ADHDを理解するうえで大切なのは、症状が本人の努力不足や性格の問題ではなく、脳の特性によるものであることを知ることです。
その理解が、本人の安心感や生活の質の向上につながります。
学習障害(LD:Learning Disabilities)は、全体的な知的発達に遅れはないにもかかわらず、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」といった特定の学習能力に著しい困難を抱える状態です。
学習障害も、本人の努力不足や家庭環境や教育環境の問題によって生じるものではありません。学習における特定の分野だけがうまくいかないため、周囲からは誤解されやすく、本人や家族が強いストレスを感じることがあります。
LDは大きく三つのタイプに分けられます。
読字障害(ディスレクシア)
・文字を正確に読むのが難しい
・行や単語を読み飛ばしたり、文章の理解が困難
書字障害(ディスグラフィア)
・文字を書くのが苦手、形や大きさが安定しない
・頭の中では文章が作れるが書き出せない場合も
算数障害(ディスカリキュリア)
・計算や数の概念の理解が難しい
・九九や文章問題が苦手、金銭管理が困難な場合も
ここでも大切なのは、特定の学習分野の困難は本人の努力不足ではなく、脳の情報処理の特性によるものであることを知ることです。こどもが安心して学びを進められる環境を作り、サポートしてあげることが大切です。
ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障害)の3つのタイプは別々に存在するわけではなく、1人のお子さんが複数の特性を持つことは珍しくありません。
例えば、ASDとADHDの両方の診断を受けるお子さんや、ADHDとLDの特性を併せ持つお子さんもいます。
同じ「授業に集中できない」という行動でも、その背景にはさまざまな理由が考えられます。もしかすると注意散漫なADHDの特性が原因かもしれません。あるいはASDの特性として、特定のことに没頭してしまう、教室の騒音が気になってしまう、といったことが原因のこともあります。またLDの特性で、先生の話や板書の内容が理解できず授業についていけない場合もあります。
このように、見た目は同じ行動でも、そこに隠れた原因はお子さんごとに異なります。
診断名だけで「こういう子」と決めつけるのではなく、行動の背景にある認知や特性を理解し、それぞれのお子さんに合った支援を考えることが大切です。
困ったときや判断に迷ったときは、無理に自分だけで考え込まず、専門の医療機関や発達支援機関に相談してみましょう。
お子さんに発達障がいの可能性があると感じたら、一人で悩まずに相談して診断を受けることが大切です。
ネットの情報は、お子さん一人ひとりの特性や状況に必ずしも合った対応ではありません。
また、保護者自信が不安な状態で情報を集めすぎると、かえって不安が強くなってしまう場合もあるでしょう。
専門機関に相談をすることで、お子さんに必要な支援をより正確に受けることができます。
ここでは、相談先と受診の流れを分かりやすく整理しました。
かかりつけ小児科
まずは日頃診てもらっている小児科に相談しましょう。必要に応じて、児童精神科や小児神経科などの専門医を紹介してもらえます。
地域の保健センターや子育て支援窓口
発達や子育ての相談ができ、地域の支援制度やサービスについても案内してもらえます。
園や学校のスクールカウンセラー
学校での様子を相談したり、先生と連携して必要な支援を検討してもらうことができます。
専門機関
児童相談所や発達障がい者支援センターなどでは、診断や療育、具体的な支援の相談が可能です。
予約・問診票の記入
初診前に、お子さんの困りごとやこれまでの経緯を簡単にまとめて問診票に記入します。母子手帳や育児日記、学校の通知表などがあれば、診断の参考になります。
初診(医師との面談)
医師が現在の困りごとだけでなく、こどもの発達歴や学校での様子、家庭での生活について詳しく聞き取ります。
各種検査
必要に応じて、心理検査や発達検査、知能検査などを行い、お子さんの得意・不得意の差を客観的に確認します。また、他の病気の可能性を確認する検査が行われることもあります。
診断
医師は面談や検査結果、保護者や学校からの情報を総合して診断します。DSM-5などの診断基準に基づき、専門家が判断します。
支援や治療方針の決定
診断結果をもとに、療育プログラムや家庭・学校での環境調整、必要に応じて薬物療法など、今後の支援や治療の方法を保護者と相談しながら決定します。
診断を受けることは、決して「こどもにラベルを貼ること」ではなく、特性を理解して適切な支援を考えるための第一歩です。
診断結果をもとに、家庭や学校での工夫、療育や支援サービスの利用など、こどもがより安心して成長できる環境を整えていくことができます。
発達障がいにおける療育とは、発達に特性があるこどもが自分らしく生活できる力を育てるための取り組みです。
こどもが自信を持ち、毎日の生活に必要な力や人との関わり方を身につけ、将来の自立に向けた土台を築くことを目的としています。
診断の有無に関わらず、気になることがあれば相談することがすすめられます。
小さいころから療育を始めることは、いじめや不登校、気持ちの落ち込みといった二次的な問題の予防につながります。
また、こどもが本来持っている力を最大限に発揮できる環境を整えることにも役立ちます。幼児期の経験や成功体験は、その後の生活や学びの基盤になるため、早めに適切な支援を受けることが望ましいとされています。
療育では、こども一人ひとりの特性に合わせて生活や運動、考える力、コミュニケーション、社会性などの分野で支援を行います。
個別療育では一人ひとりの困りごとに合わせた細やかなサポートが可能となり、
集団療育では同年代のこどもたちとの関わりの中で社会性やコミュニケーション能力を自然に身につけられます。
療育サービスは、通って利用する「通所型」と、施設で生活しながら受ける「入所型」に分かれます。また、福祉中心の支援と医療も含む支援の2種類があります。以下は概要です。
通所型
通所型は、地域で生活しながら日中の時間に支援を受ける形で、多くの療育施設がこのタイプです。特に児童発達支援や放課後等デイサービスは、利用者も多く、個別の特性や困りごとに合わせた支援を受けられます。
| 施設種別 | 主なサービス | 対象年齢 | 対象となる障がいの種類 | 主な支援内容 |
|---|---|---|---|---|
| 福祉型 | 児童発達支援 | 0〜6歳(未就学児) | 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい含む) | 日常生活動作指導、生活能力向上訓練、知識技能付与、集団生活適応訓練 |
| 福祉型 | 放課後等デイサービス | 小学生〜高校生(原則18歳まで) | 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい含む) | 日常生活支援、学習指導、地域交流、自立支援 |
| 福祉型 | 保育所等訪問支援 | 全年齢 | 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい含む) | 専門スタッフが保育園等を訪問し、集団生活への適応を支援 |
| 医療型 | 医療型児童発達支援 | 未就学児(身体障がいが主) | 身体障がい(重症心身障がい児など) | 疾病の治療・看護、医学的管理下の介護、機能訓練 |
入所型
入所型は、より集中的な支援が必要な場合や家庭での生活が困難な場合に利用され、施設で生活しながら24時間体制で支援を受ける形です。
| 施設種別 | 主なサービス | 対象年齢 | 対象となる障がいの種類 | 主な支援内容 |
|---|---|---|---|---|
| 福祉型 | 福祉型障がい児入所施設 | 全年齢 | 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい含む) | 介護サービス、相談支援、機能訓練、社会活動参加支援 |
| 医療型 | 医療型障がい児入所施設 | 全年齢 | 重度の障がい(医療的ケアが必要な場合が多い) | 疾病治療・看護、医学的管理下の介護、機能訓練、社会活動参加支援 |
療育サービスを利用するには、市町村が発行する受給者証が必要です。
相談窓口や相談支援事業所を活用することで、施設の選び方や申請手続き、利用計画書の作成まで幅広くサポートを受けられます。
正式な診断がなくても、発達に少しでも気になる点がある場合には相談することができます。
療育はすぐに効果が現れるものではありませんが、時間をかけて少しずつ成果が感じられる取り組みです。「できた!」という経験を積み重ねることで自己肯定感が育ち、日常生活で必要な力や社会での関わり方が身につきます。早期から適切な支援を受けることで、こどもの将来の可能性を大きく広げることができます。
こどもの発達障がい療育の具体的な内容について詳しく見る
発達障がいは、個人だけの問題ではなく、社会問題として理解し支えることが大切だと考えられています。
お子さんが安心して暮らし、自分らしさを伸ばせる社会を作るには、家庭での理解はもちろん、学校や職場、地域での支援や配慮も欠かせません。
ここでは、教育や社会の取り組み、支援の考え方についてわかりやすく解説します。
インクルーシブ教育とは、障害の有無にかかわらず、すべてのこどもが同じ学びの場で学べるように配慮する教育の考え方です。
特別支援学級や特別支援学校だけでなく、通常学級で学びながら必要な支援を受けることができます。お子さん一人ひとりに合った教材や環境を整え、学習参加を可能にすることで、能力を最大限に伸ばせることが目指されています。
関連記事:
合理的配慮とは、障害のあるお子さんが障害のないこどもと同じスタートラインで学びやすくするための調整です。
これは特別な優遇ではなく、「社会の障壁を取り除く」ための工夫です。
例えば、読み書きが難しい子にはタブレットの使用を認める、聴覚過敏の子にはイヤーマフを使えるようにする、板書が苦手な子には写真撮影を許可するなどがあります。
職場でも同じ考え方が適用されます。口頭での指示が苦手な人にはメールで伝える、マルチタスクが苦手な人には業務の優先順位を明確に示す、感覚過敏に配慮して座席を調整する、などです。合理的配慮は、社会にある「障壁」を取り除き、平等に参加できる環境を整えるための工夫です。
「発達障がいは個性である」と表現されることがあります。これは、多様性を尊重し、ポジティブに障害を捉える意図からきています。
メリット
一方で、「個性」という表現だけでは、お子さんが直面する困難や生きづらさを十分に理解できない場合があります。服薬や通院、日常生活での努力、社会の偏見など、実際の課題は「個性」だけで片付けられないのが現実です。
発達障がいについては、まだ誤解や不安が多く、親御さんの中には「自分の育て方が悪かったのでは」と悩む方も少なくありません。
ここでは、よくある疑問や誤解に対して、科学的な知見に基づいた正しい理解を分かりやすく解説します。
いいえ、全く違います。発達障がいは生まれつきの脳機能の特性によるもので、育て方や愛情不足が原因ではありません。これは多くの研究で明らかになっている事実です。親の関わり方に自信が持てなくても、責める必要はありません。
いいえ、発達障がいは後天的に発症するものではありません。大人になって診断されるケースでは、こどもの頃は目立たなかった特性が、社会生活の要求が増えることで顕在化しているだけです。
一部の人は、特定の分野で優れた能力を発揮することがあります。たとえば、ASDの「過集中」や強い探求心が専門分野で才能として開花する場合もあります。しかし、全員がそうではなく、多くの場合は日常生活で困難も伴います。才能の面だけを強調すると、当事者の生きづらさを見過ごす危険があります。
診断にはメリットとデメリットの両面があります。メリットは、自己理解が深まり、必要な支援や合理的配慮を受けやすくなることです。一方で、人によっては偏見やスティグマを感じる可能性もゼロではありません。診断をオープンにするかどうかは本人が決められますが、法的な保護や支援を受けるためには重要なステップとなります。
まずは、発達障がいの特性を正しく理解することが第一歩です。「普通」を基準にせず、本人の困りごとに耳を傾け、「どうすればできるか」を一緒に考える姿勢が大切です。具体的には、視覚的なサポートや安心できる環境の整備、具体的な指示の提供などが有効です。

「うちの子はぬいぐるみが好きで手放せない…。これって発達障が...

こどもが社会の中で上手に関わり合いながら成長していくためには...
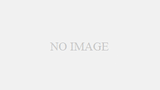
「発達障害」の認知度は、少し前と比べても 格段に上がってきて...
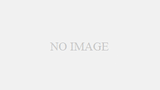
発達に遅れや偏りのある子ども達と接していると、 一見理解しが...
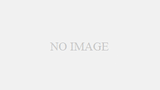
発達障害を持つ子ども達の中には、 「疲れやすい」と感じている...

適応行動・不適応行動という言葉を耳にしたことはありますか? ...
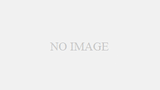
ASD(自閉症スペクトラム)やADHDなど発達障害では、注意...
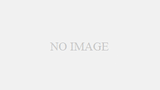
発達障害のある子ども達では、もともと筋力が弱かったり、 ボデ...
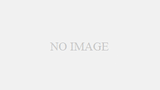
発達障害は様々です。 それぞれが重なり合っていて、 スペクト...