こどもには「できなかったことができるようになる」経験が大切です!
 発達障害
発達障害こども達は、日々の生活の中で多くのことを学び、色々なことができるようになっていきます。
こどもにとって、できなかったことができるようになるという経験はとても重要です。
発達支援の現場では、この「できなかったことができるようになる」瞬間に計り知れない価値があります。
こどもの小さな一歩が、その子の人生を大きく変える可能性を秘めているからです。
本記事では、発達支援の専門的知見と実践経験をもとに、お子さんの「できる」を引き出すための具体的な方法をご紹介します。
できなかったことができるようになるために「できない」の原因を理解しよう
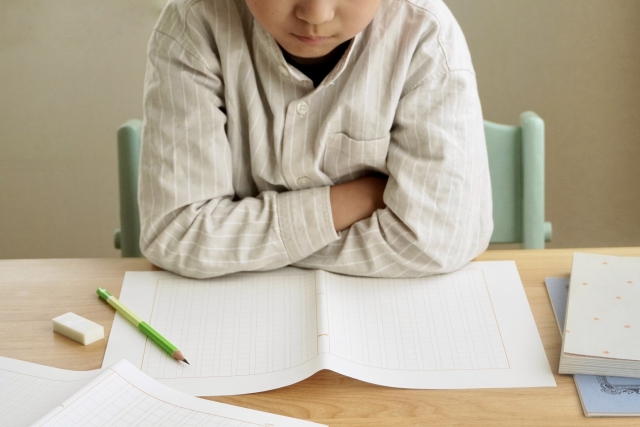
「できなかったことができるようになる」ためには、まず「できない」理由を正確に理解することが出発点です。
発達障がいや発達の遅れがあるこどもたちの「できない」には様々な背景があり、適切な原因理解があってこそ効果的な支援が可能になります。
発達障がいの特性別「できない」の背景と支援アプローチ
発達障がいの種類によって「できない」理由は大きく異なります。
自閉スペクトラム症のお子さんは、指示の理解や状況把握が難しく、「何をすれば良いか分からない」ことが「できない」の原因になりがちです。
一方、注意欠如・多動症のお子さんは、注意の持続や行動のコントロールの難しさから「分かっているけどできない」状態になることが多いです。
例えば、算数の文章題が解けないお子さんの場合、問題文を最後まで読み切れないことが影響していることがあります。
このような場合は、問題文を短く区切って提示したり、重要な数字に色付けをしたりする工夫が効果的です。
感覚・認知・運動など機能別に見た「できない」の理解と対応
「できなかったことができるようになる」には、こどもの感覚・認知・運動能力などの機能別特性を詳細に理解することが不可欠です。
同じ「字が書けない」という状況でも、原因は様々です。
感覚処理の問題
- 触覚過敏でペンの感触が苦手
- 姿勢保持が難しい
- 視覚的な情報処理が苦手で文字の形を認識しづらい
認知面の問題
- 空間認知が苦手で文字のバランスがとれない
- 記憶の問題で文字の形を覚えられない
- 言語理解の問題で文字の意味と結びつかない
運動面の問題
- 手先の微細運動が未発達
- 書く動作の順序が分からない
- 左右や上下の認識が難しい
支援現場では、これらの要素を細かく見極め、的確な支援につなげることが重要です。
例えば、ハサミが使えないお子さんには、指先の力や両手の協調性を段階的に育てる支援が効果的です。
こどもの強みと特性を活かした「できる」を引き出す視点
「できなかったことができるようになる」最大の鍵は、こどもの苦手にばかり目を向けるのではなく、強みや得意な部分を活かしたアプローチです。
これは発達支援において最も見落とされがちな視点かもしれません。
こどもの得意な認知チャンネルや興味を活用することで、難しい課題も取り組みやすくなります。
視覚優位なこどもの場合
- 文字による指示が難しければ、絵やイラストで伝える
- 手順書や視覚的なスケジュールを活用する
- 文字の学習も絵カードと組み合わせる
聴覚優位なこどもの場合
- リズムや音楽を使って記憶を促す
- 口頭での説明を丁寧に行う
- 自分で声に出して確認する習慣をつける
運動感覚が得意なこどもの場合
- 体を動かしながら学習する機会を増やす
- 空中に文字を書く練習を取り入れる
- 粘土など触覚を使った教材を活用する
長文読解が苦手なお子さんが、図や表を使って内容を整理することで理解度が向上することがあります。
また、特別な興味(例:電車、恐竜、アニメキャラクターなど)を学習の入り口として活用することも効果的です。
「できなかったことができるようになる」ためには、こども一人ひとりの強みと特性を見出し、それを活かした支援を心がけることが大切です。
次の段落では、より具体的な環境設定と支援テクニックについて解説します。
こどもが「できた!」を体験できる支援のコツ

こどもが「できなかったことができるようになる」ためには、こどもが成功しやすい環境と、やり方をわかりやすく伝える工夫がとても大切です。
やさしい環境とわかりやすいサポートがあれば、こどもは自信を持ってチャレンジでき、新しいことも少しずつできるようになっていきます。
見てわかるサポートと、わかりやすい活動の流れづくり
こどもが「できた!」と感じるために必要なのは、見てすぐにわかるサポートと、わかりやすく整理された環境です。
特に、発達に特徴のあるお子さんは、耳で聞くよりも、目で見て理解することが得意なことがあります。
わかりやすい見た目の工夫があることで、混乱や不安が減り、「できた!」が増えていきます。
「見てわかる」サポートの例
1.手順の表やチェックリスト
- 朝のしたく、宿題のやり方、お片付けの順番など
- 文字だけでなく、写真や絵を使うとより分かりやすい
- できたらチェックを入れて、達成感も味わえる
2.時間が見えるタイマー
- あと何分かが目で見て分かると、先の見通しが立つ
- 不安が減って、集中力もアップ
3.場所のわかりやすさ
- 物の置き場所に写真や絵のラベルをつける
- 床にテープを貼って、エリアを分ける
- やることごとに使う場所を分けると混乱しにくい
たとえば、保育園で着替えが苦手なお子さんに、ロッカーに写真つきの着替え手順を貼ることで、自分のペースで着替えができるようになることがあります。
周りの環境が分かりやすくなることで、こどもは自分の力をもっと発揮できるようになります。
「時間」「場所」「やること」の順番や使い方が整っていると、こどもは先の見通しが立てやすくなり、安心して行動できるようになります。
成功体験を確実に積み重ねる「スモールステップ」の設定
適切なスモールステップを設定し、一つひとつ確実に成功体験を積み重ねていくことも重要です。
こどもにとって大きな目標をいきなり達成することは難しくても、小さな一歩なら踏み出せることがほとんどです。
効果的なスモールステップの設定方法
- 現状の正確な把握から始める
- できることとできないことを客観的に観察する
- 「もう少しでできそう」なポイントを見つける
- こどもの意欲や関心も考慮する
- 適切な難易度の設定
- 成功率が80%程度になるよう調整する
- 少し頑張れば達成できるレベルを狙う
- 達成したら少しずつハードルを上げていく
- 具体的な行動レベルで目標を設定する
- 「集中力をつける」ではなく「5分間席に座って課題に取り組む」
- 「コミュニケーション力を高める」ではなく「あいさつができる」
- 測定可能な形で設定する
鉛筆で文字を書くことに抵抗があるお子さんには、指で砂文字盤に書く→太めのクレヨンで大きく書く→マーカーで点線なぞり→鉛筆で点線なぞり→見本を見ながら書く→自分で書く、といったステップを踏むことで、少しずつ「できた!」体験を積み重ねることができます。
日常生活の中で「できた」体験を増やす実践的な工夫
毎日の生活の中に「できた」体験を意図的に組み込むことで、こどもの成長を加速させることができます。
家庭でできる「できた」の体験
- 日常のルーティンを活用する
- 朝の準備、食事、入浴など日常的な活動に小さな役割を設ける
- 「牛乳パックを開ける係」「テーブルを拭く係」など
- できたらしっかり認める習慣をつける
- こどもの興味に合わせた挑戦の機会を作る
- 好きな活動の中に少しだけ難しい要素を入れる
- 例:料理が好きな子なら「計量」の役割を任せる
- 電車が好きな子なら時刻表を読む練習につなげる
- あそびの中に学びを埋め込む
- ボードゲームで順番や数の理解を促す
- なぞなぞやしりとりで言語能力を高める
- 体を動かすあそびで協調運動を発達させる
日本LD学会の調査によれば、日常生活の文脈で学んだスキルは、他の場面での応用が起こりやすいことが示されています(日本LD学会, 2019)。
特別な訓練よりも、実生活での自然な学習機会を活用することが効果的です。
「できなかったことができるようになる」ため、日々の生活の中に成功体験を積極的に取り入れ、こどもの成長を支えていきましょう。
次の段落では、「できた」体験を心理面の成長につなげる方法について解説します。
適切な褒め方で「できた」体験を自信と成長につなげよう

「できなかったことができるようになる」体験は、こどもの心理的成長に繋がります。
「できた」体験を通じて自己効力感や自己肯定感を高め、長期的な成長につなげる支援が必要です。
こどもの「できた」を効果的に褒め、自己肯定感を高める関わり方
「できなかったことができるようになる」過程で最も重要なのが、こどもの成功体験を適切に認め、自己肯定感につなげる関わり方です。
ただ漠然と「すごいね」と褒めるよりも、こどもの具体的な行動や努力を認めることが効果的です。
効果的な褒め方のポイント
- 具体的な行動を褒める
- 「頑張ったね」→「最後まで集中して取り組めたね」
- 「上手だね」→「丁寧に線の上をなぞることができたね」
- 具体的に何が良かったかを伝える
- 努力や過程を褒める
- 結果だけでなく努力のプロセスに注目する
- 「難しかったけど挑戦したね」
- 「失敗しても最後までやり遂げたね」
- 自己評価を促す言葉かけ
- 「どんな感じだった?」
- 「前よりもどこが上手くなった?」
- こども自身が成長を実感できるようにする
過程を褒めることは、こどもの挑戦意欲や粘り強さの発達に効果的です。
特に発達に特性のあるこどもたちにとって、小さな成功や努力を認められる体験は、自己肯定感の土台となります。
「できた!」の体験を通じて自己肯定感を高めるためには、こどもの具体的な行動や努力を言語化して伝え、こども自身が自分の成長を実感できるようサポートすることが大切です。
「できた記録」でこどもの成長を振り返る
目に見える形で進歩を示すことで、こども自身が自分の成長を確認でき、さらなる挑戦への意欲を高めることができます。
効果的な記録と振り返りの方法
- 「できたカレンダー」の活用
- カレンダーに毎日の小さな成功をシールや印で記録
- 1週間、1ヶ月単位で振り返る機会を設ける
- 視覚的に成功の積み重ねを実感できる
- 成長アルバムの作成
- 「できなかった時」と「できるようになった時」の写真や動画を比較
- 作品や成果物を時系列で保存
- 定期的に見返して成長を確認する
教育心理学の研究では、自己の成長を視覚化することが、内発的動機づけの促進に効果的であることが示されています(伊藤, 2016)。
特に発達障がいのあるこどもにとって、抽象的な「成長」を具体的に示すことは、自己理解と自信につながる重要な支援となります。
家庭・学校・療育の連携で「できる」を広げる
できなかったことができるようになるためには、こどもを取り巻く環境全体での一貫した支援が不可欠です。
家庭、学校、療育機関がしっかりと連携し、情報共有することで、こどもの「できる」を様々な場面に広げ、定着させることができます。
効果的な連携のポイント
- 情報共有ツールの活用
- 連絡帳や支援ノートで日々の様子を共有
- デジタルツールも活用(写真や動画の共有など)
- 成功事例や効果的だった支援方法を記録
- 共通の目標設定と評価
- 短期・中期・長期の目標を関係者で共有
- 評価基準を明確にする
文部科学省の調査によれば、特別支援教育における関係機関の連携が効果的に行われている事例では、こどもの学習成果や社会的スキルの定着率が高いことが報告されています(文部科学省, 2020)。
特に「できた」体験の他の場面への応用には、環境間の連携が決定的に重要です。
「できなかったことができるようになる」ためには、こどもを支える大人たちが情報と方法を共有し、一貫した支援を提供することが不可欠です。
それぞれの場所での小さな成功が、こどもの大きな自信と成長につながっていきます。
こどもの「できない」には必ず理由があります。
その理由を丁寧に紐解き、こどもの強みを活かした支援を行うことで、小さな「できた」体験を積み重ねていくことができます。
そして最も重要なのは、「できた」体験を通じてこども自身が自分の可能性を信じられるようになることです。
できなかったことができるようになる瞬間は、こどもの人生における大きな転機となります。
その瞬間を共に喜び、次の挑戦へとこどもを導くための支援をしていきましょう。
- 日本LD学会 (2019) 『発達障がい研究の最前線』 金剛出版
- 伊藤崇達 (2016) 『自己調整学習の理論と実践』 北大路書房
- 文部科学省 (2020) 『特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議報告』





